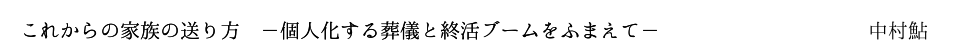
目次
序論
1章 多様化する葬儀の形
1.1 変わりつつある葬儀
・1.1.1 葬儀の小規模化、低価格化
・1.1.2 自分らしい葬儀への関心の高まり
1.2 無宗教葬という選択の意味
1.3 個人化する葬儀の背景
2章 葬儀の事前準備について
2.1「終活」ブームの到来
2.2 エンディングノートと生前予約システムについて
2.3 終活ブームの背景とふたつの局面
3章 これからの葬儀について
3.1 葬儀の意義
3.2 葬儀のあり方の急速な変化への考察
・3.2.1 葬儀の簡素化、低価格化について
・3.2.2 仏教と葬儀の関係についての考察
3.3 葬儀は誰のためのものか―終活にみる送り手の不在―
3.4 葬儀の個人化を受けて―故人らしさの演出―
結論
参考文献一覧
序論
本研究は現在の日本における「よい葬儀」とは何かを考え、家族を送るための新しい葬儀を提案することを目的とする。
葬儀について、家族の死後について、家族と話をしたことはあるだろうか。 葬儀はかつて決まった慣習にのっとり、決められた通りに行われていくものだった。 よって自分が望む葬儀の形などということは考えうることでは無かった。 また、葬儀などの死にまつわる話題は「縁起でもない」というように避けられていた。しかし、この20年で葬儀を取り巻く状況は大きく変化した。 以前はタブー視されていた葬儀に関する話題がメディアに頻繁に登場するようになり、ワイドショーでも特集が組まれるようになった。 この数年で「終活」という言葉まで台頭した。自分の葬儀を自分で準備するなどということは、今までには考えられなかったことである。 世の中の葬儀に対する考え方が大きく見直されてきていると言える。社会のあり方が急速に変化している中で、葬儀はどのように変わったのか、それが何を意味するのかを今問い直すことは意義があると思われる。 特に葬制研究の中でこの20年の動向はまだ深く扱われておらず、著書の中でも新しい傾向を紹介するに留まっているものが多い。 社会が変わり、家庭環境も変化する中で、これから私たちにとっての「よい葬儀」とは何か、そのために何ができるのか考えていきたい。
また、本論文は子どもが親を送る葬儀を前提として結論を出していく。 中学生のころ、祖父の葬儀の際に父親から「自分の葬儀の時には、お坊さんは呼ばずに余計なお金をかけないで欲しい」というような希望を初めて聞き、葬儀かたちを将来自分が選ばなくてはいけないということに気付いた。 そのことがきっかけで葬儀に対して興味を持っていたことが本論文に取り組む動機となっている。 その頃から、日頃信仰心のない日本人がなぜ葬儀の折にだけ、高額なお布施を支払い、仏式で葬儀をあげるのか疑問に思ってきた。 この疑問は、無宗教葬という選択が実際に可能になった現在、改めて問い直す価値があるのではないだろうか。 そもそもこの疑問自体、正しいことなのだろうか。仏教と葬儀の関係を問い直し、私たちがこれからどう向き合っていくべきかも、本論で示唆したい。
1章では、ここ数年で新たに台頭してきた葬儀形式を調査し、その傾向を探る。 葬儀の形態は多様になってきており、私たちは選択を迫られているといえる。 アンケート調査を用いて、どのような葬儀が求められているのかという点も合わせてみていく。 1節では葬儀の新しい傾向として、小規模化と低価格化していること、自分らしい葬儀に対して関心が高まってきていることについて述べる。 このニーズに対応して葬儀社は、小規模で、低価格に葬儀をあげられるプランをつくるようになってきており、一部では葬儀の簡素化、合理化が進んでいると言える。 2節では選択肢のひとつとしてあげられる無宗教葬について論ずる。無宗教葬が世間ではどのように認識されているのか、実際に行われている件数はどの程度なのか、アンケート調査を用いて分析する。 1節、2節であげた新しい葬儀の傾向は、葬制研究のなかで「個性化」と呼ばれている。3節では葬儀が「個性化」してきた社会的背景について述べる。
2章では、葬儀に対する世の中の新しい見方、考え方について、「終活」をキーワードに述べていく。 1節では「終活」はまだ新しい言葉と言えるのでこれがいかなるものなのかという説明を行う。去年開催され、新聞で取り上げられていた終活フェアを例に紹介する。 2節では終活において大きな位置を占めるエンディングノートと、生前予約システムについて紹介し、分析する。自らの老後や死後に備えての準備という点では同じ目的をもっているものであるが、実際の効果や使われ方は異なると考えられる。 3節では「終活」という言葉ができ、ブームとなってきた背景について述べる。これには積極的に評価される面と、そうせざるを得ないという社会的要因によるもののふたつの局面があると考えられる。
3章では1,2章で述べた葬儀を取り巻く現状を踏まえて、これからの「よい葬儀」のあり方を探る。 1節ではまず、時代と共に変わるものではない、葬儀の意義について述べ、葬儀の役割を考え直す。 2節では、1章で述べた葬儀の簡略化や、無宗教葬について考察し直し、主張を行う。 故人をゆっくり偲ぶことができるようにと、合理化、簡略化された葬儀は本当に遺族のためになっているのだろうか。 また、1節で葬儀の意義について述べたことを踏まえ、宗教は葬儀に必要であるという考えを主張する。3節では、葬儀は誰のためのものかという問いを呈し、答えていく。 2節で論じた、無宗教葬が望まれていても普及していない理由から、葬儀は誰のためのものか、誰にとっての「よい葬儀」であるのかという問いが生じたことにたいして、本論文では葬儀は遺族のためのものであるとして主張する。 4節では、上述したここ数年の葬儀の傾向や、望まれている葬儀のかたちを踏まえたうえで、これからの家族を送る「よい葬儀」のあり方として「故人らしさ」を演出した葬儀があるのではないかという結論に結び付ける。 5節では「故人らしさ」を演出した葬儀を進めた場合に生じると予測できる問題点について述べ、解決策を提案する。
結論には全体のまとめと、3章4節から述べてきた主張を、実現するために考えられる方法を提示し、「故人らしい」葬儀をこれからの葬儀のあり方として提案する。
以上が本論文の構成である。
ここで「葬儀」という言葉を使うことに対して説明が必要である。 葬儀とは葬送儀礼のことで、遺体と魂への対応である。故人と親族が一緒に過ごし、僧侶の読経と共に魂を弔う儀式である。通夜がこれにあたる。 これに告別式を合わせたものを葬式と呼んでいるのである。告別式とは社会に対して故人の死を知らせるものである。告別式が葬儀と分けて出てきたのは都市化による影響で、昭和30年代からである。 それ以前の葬儀では、死者の出た家に近所の者が集まり儀礼を行い、会食をし、遺体を埋葬するために墓地に葬列をなすことがメインとなっていた。 ところが都市化によって個人の人間関係は外に広がり、葬儀に参列する人数が増えてくる。自宅では収容しきれないため、葬儀は儀礼に限定し、共同対外の参列者に対しては葬儀とは別に告別式という形を行うようになった。 現在ではこのかたちも変わってきている。通夜、告別式という言葉は分けて使っているものの、実際はあまり変わりがなくなってきている。通夜は夕刻から始まるため、通夜だけに参列するというケースが多くなってきたためだ。 また、僧侶の読経と共に参列者は焼香をはじめ、葬儀と告別式が同時並行されている。
本論文では、一般的に通夜に始まり告別式、火葬までを含めた「葬式」を扱うことになるが、告別式が社会的儀礼として50年ほど前から台頭してきたこと、そして現在またその境目が曖昧になってきていることを受けて、「葬儀」という言葉を統一して用いることとする。
1章 多様化する今日の葬儀のかたち
1.1 変わりつつある葬儀
1995年頃から、特に都市部で葬儀のためのセレモニーホール、いわゆる斎場の建設ラッシュが起こる。 自宅で葬儀をあげることが激減し、同時に、この頃から葬祭業社は簡素化、小規模化をキーワードに新たな葬儀のスタイルを提案し、世に普及していくこととなった。 1章ではその多様化した葬儀のかたちをキーワードごとに見ていく。
・1.1.1 葬儀の小規模化、低価格化
葬儀一式にかける費用は年々減少傾向にある。 2010年実施の第9回「葬儀についてのアンケート調査」 によれば、葬儀一式(通夜からの飲食接待費、お経料や戒名、お布施等寺院の費用を除く)の費用は全国平均で126.7万円である。 この調査は3年毎に行われており、前回の調査の2007年は142.3万円、前々回の2004年は150.4万円であった。 飲食代や寺院へ支払った費用を含めた葬儀費用の合計額も、2007年の調査では231万円、2010年の調査では199万円であり、14%近く減少していることがわかる。 このことから、この10年ほど葬儀費用は減少傾向が続いていると言える。 葬儀費用の低価格化は、葬儀の小規模化、簡素化の影響と言えるだろう。高齢化が進んだことによる参列者の減少や、親族のみで行う葬儀の増加をうけ、葬儀社が名付けた葬儀のあり方が「家族葬」である。 現在、ほとんどの葬儀社に「家族葬」と名付けられたプランが存在し、かなり一般的になってきているといえよう。 家族葬の定義ははっきりと決められているわけではないが、家族葬と呼ばれる大きな要因の一つは参加者の範囲であり、近い親族やごく親しい友人数名のみで行われるものという認識が一般的である。 その結果、傾向としては低価格になるものの、低価格であること、簡素であることが家族葬というわけではない。家族のみでゆっくりとお別れをしたいという理由でこういった小規模な葬儀を選ぶケースが増えている。 対して、「直葬」やワンデーセレモニーと呼ばれるものは、「価格重視」や「(余計な手間を省いくという意味で)簡素」などの消極的理由で選ばれるものという認識が強いようである。 これらは故人が亡くなった後、自宅や葬儀社が用意する一時的な安置所に遺体を搬送、近親者だけで通夜を行い、告別式は行わずに翌日に火葬を行うものである。僧侶は介在しないのが一般的であるが、その限りではない。 家族葬との間に言葉によるイメージの違いはあるものの、式の流れそのものは、外から見て大きく変わるものではないともいえる。 火葬をメインとした直葬などは、最も安価と思われるものは69.800円から存在し、10万円代というプランが多い。 家族葬プランの幅は広いが、それでも20万円代から50万円代までの価格帯で存在し、全国平均から考えるとかなりの安価で葬儀をあげることができるようになってきている。(寺院への費用は別。)
また、「葬儀についてのアンケート調査」では「自分自身の望ましい葬儀のかたち」という問い(回答は選択式)に対し、63.2%の人が「費用をかけないで欲しい」を選択し、一番多い回答率であった。 次いで多かったものが「家族だけで送ってほしい」という選択肢で44%である。このことからも葬儀の小規模化、低価格化は今後も進むと考えられるだろう。
・1.1.2 自分らしい葬儀への関心の高まり
上記にあげた低価格化、小規模化の一方で、葬儀を自分らしく行いたいという思いから式をそのらしくアレンジする傾向もみられる。 このような葬儀が「自分葬」と呼ばれるようになってきている。 式の前後にスライドや映像を用いて自分史を紹介するという試みや、焼香の代わりに故人の好きだった花や酒類などを捧げるということも珍しいことでは無い。 故人の好きだった音楽を流す、参列者が演奏をすることなども、葬儀社に相談すれば可能である。 伺った葬儀社の人の話によれば、葬儀会場に故人の趣味の品や写真などを飾る「思い出コーナー」を設ける程度であれば、追加費用もさほどかからないため、取り入れる遺族も増えてきているという。 また、正確には葬儀ではないが、生前葬と称して生きているうちに、生前お世話になった人々を集めてお別れの会を開くという例もみられる。 もちろん斎場を用いることはできないのでホテルなどの宴会場を借りて行われる。
また、最近特に話題となっているのが樹木葬や散骨といった埋葬方法である。 従来は葬儀のあと、四十九日で墓へ納骨することしか考えられていなかった。 しかし現在は遺骨をどうするかということまで選択肢が広がっているのである。 散骨とは、骨灰を海中、山中、空中にまく葬法である。散骨が世に知られるようになったのは、1991年、市民団体「葬送の自由をすすめる会」が、ある人物の遺骨を海に流し、社会問題となったことにある。 「葬送の自由を進める会」は現在NPO法人となって会員制という形をとって自然葬のサポート活動をおこなっている。 最初に行われたこの自然葬を、厚生省は現行の「墓地、埋葬等に関する法律」は散骨を想定していなかったことから、同法に抵触するものではないと述べ、法務省も「葬儀として節度をもってなされれば遺骨の生きには当たらない」という見解を示した。 このことによって「骨は撒いてもよい」という風潮が急速に広まってきた。これを受け、葬儀社でも散骨を請け負うところがでてきた。 散骨のためのクルーズを専門に扱っているサービス会社もある。 散骨を海洋葬と命名し、遺骨を自然にまくことで自然に返すという考え方のもとに行われる。 2000年になると、庭園式の墓地、樹木葬専用霊園が登場する。 樹木葬と呼ばれるものだ。木や花の下に遺骨を撒くことで、自然となって生まれ変わるというコンセプトが支持を得てきている。 一人の遺骨につき一区画のスペースを使用し、遺族にとってメモリアルとなる場所を残せるものから、合葬形式で一切区切りを設けないタイプの霊園も存在する。 樹木葬は「遺骨を自然に還す」という発想においては散骨に近い。 違いの一つは、散骨が墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の枠外のこととして行われているのに対し、都道府県知事の許可を得た墓地で行うという墓埋法の枠内で行われることである。 そのため散骨よりも受け入れられやすく、生前予約で埋まっている霊園まであるという。
従来の形式、風習などに囚われずに葬儀を執り行いたいという人が増え、それをよしとする風潮が広まっていると言える。 先程も引用したアンケート調査「自分自身の望ましい葬儀のかたち」という問いで「地域のしきたり、家族のしきたりがあるので、それに従ってほしい」と答えた人が16.8%にとどまっていることからもこのことがわかる。 散骨も、20年前は違法として認識されていたのだから急激な変化といってよいだろう。
1.2 無宗教葬という選択の意味
私の研究動機にもあげたように、父親は自分の葬儀はできればお坊さんを呼ばずに行って欲しいというような思いでいる。 葬儀が多様化する中で、無宗教葬という選択肢もでてきたのだ。 「葬儀についてのアンケート調査」では、この3年に葬儀を経験した回答者に葬儀の形式を問うと、仏式が90.1%、神式が3.4%、キリスト式が1.4%となっており、無宗教葬という形をとった人は2.4%に留まっている。 やはり仏式が主流であることに変わりはない。しかし、この「仏式」は僧侶の介在によって定義されるものではない。 つまり、祭壇や仏具(という言葉自体が仏式を表してしまうのだが)を一般的な仏式のものを用いて行った場合であれば、僧侶を呼ばずとも仏式と回答していると思われる。 よって無宗教葬という認識はなくとも「僧侶を呼ばない葬儀」はこの回答数よりも多く存在していると考えてよいだろう。 しかし、昨年の読売新聞による「冠婚葬祭」世論調査 をみると、「自分の葬式は、宗教色のない葬儀にしてほしいと思いますか。」という問いに対し、48%の人が「そう思う」と回答している。 4年前の2008年8月に行われた読売新聞「宗教」世論調査では同じ問いで「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた人を合わせて39.6%であったことから、無宗教葬を望む、無宗教葬でもよいと考える人々は増加傾向にあると言ってよいだろう。
ここで考えたいのは、無宗教葬を望む人々にとってそれが積極的な選択であるのか、消極的な選択であるのかという点である。 自分の最期をそれまで縁のなかった僧侶に依頼したくない、特定の宗教に頼りたくないという信念のもとに本人がそう望む場合と、日頃信仰心を持たず、菩提寺との付き合いもないため、葬儀をお寺に依頼する意義がわからず、無宗教で葬儀をあげるというよりは、読経を「省く」という感覚で行われる場合では大きく意味が異なると言える。経済的な理由から僧侶は呼ばなくてもよいと考えている場合もあるだろう。 本人の希望であってもただ「家族に迷惑をかけたくない、簡素にしてほしい」という理由であれば積極的な選択とは言い難い。線引きは難しいが、無宗教葬と一概に言っても選択の理由によって意味が全く異なる。
1.3 個人化する葬儀の背景
上述したような葬儀の小規模化、家族を中心とした葬儀が主流になってきていることを指し、葬儀が「個人化」していると表現されることが多い。 その理由は、社会的背景から2つある。それが高齢化、核家族化である。 高齢化率が上昇し2007年、超高齢社会へ突入した。平均寿命は大きく伸びている。 高度経済成長期の1960年と2011年を比較すると、男性は65歳から79歳に、女性は70歳から85歳になっている。 年間死亡者数は80歳以上が全体の半数を超えているのが現状だ。死者が高齢化すれば参列者も高齢化し、高齢者になると葬儀のために田舎から都市へ出ることも困難な場合が多い。 よって家族のみでの小規模な葬儀が主流となってきているのは当然といえる。また核家族化、家庭の流動化により、規範となるイエがなくなることで葬儀の自由化が進んだとも言える。
葬儀にはそれぞれの地域社会において、規範となるコンセンサスがあり、その下で行われていた。 地域共同体が生きていた時代、ある家族に死者が出てその家が弱くなり、それがきっかけで共同体自体の弱体化を招かないように、その家の弔いを手伝い、遺族が喪に専念できる環境をつくるという相互扶助のシステムがあった。 同時にそれぞれの家の勝手を許さないという規範であったと言える。 現在都市部では地域の付き合いは軽薄化し、地域共同体という枠組みが外れ、葬儀は完全に各家庭に任されることとなった。そして、葬儀は完全に葬儀社の手に委ねられることとなった。 これに関しては、自宅で死を迎える人の数が減少したことも葬儀のかたちや場所が変化してきた大きな理由である。
平成3年の厚生省の記録によれば、70歳以上の高齢者が自宅で死を迎える割合は全国平均で27.3%であり、残りの72.7%が自宅以外の病院や施設で最期を迎えているという。 ちなみに昭和30年代では、病院などで死を迎える人は3割、自宅で死を迎える人が7割と逆であった。30年近くで死の環境も大きく変わったことがわかる。 1990年代になり、急速に葬儀の場が自宅や寺院から葬儀専門斎場に移行するようになった。このように、社会の変化とともに死の環境も変わり、地域のしきたり、慣習による縛りがなくなったことにより、自分らしい葬儀という考え方が出てきたといえる。 そもそも地域共同体の公的行事であったものを「自分らしく」と「個」を中心に考えるようになってきたことは、葬儀の個人化の極致といえるだろう。 これら2つの社会的要因を受け、葬儀のあり方を見直す動きが出てきた。高度経済成長期以降、派手で豪華な葬儀こそが立派な葬儀とされてきた。 ある会社員の親の葬式に、同僚や部下、取引先の人まで参列するなど、故人を知らない人までもが多く参列するようになったのも、生け花で祭壇が豪華に飾られるようになったのもこの時期からである。 こうして必要以上に葬儀が大きくなり、葬儀が形骸化したことに対して反省するような考え方が出てきたのがこの15年ほどであるといえよう。
2章 葬儀の事前準備について
2.1 「終活」ブームの到来
「終活」という言葉をよく耳にするようになった。 終活とは、広義に人生の最期を自分の望むように自分で準備することである。 この言葉は、週刊朝日で2009年に連載された「現代終活事情」で知られるようになり、『現代用語の基礎知識』には2010年版から掲載されている。 昨年には終活本の出版やメディアで取り上げられることが飛躍的に増え、2012年のユーキャン新語・流行語大賞ではトップテン入りしている。 全国各地でエンディングノートの書き方、葬儀の準備に必要なことをテーマにした講演が盛んになってきており、ワイドショーでもその様がとりあげられるようになった。 とくに神奈川県の川崎市では活動が盛んであり、昨年9月28日、川崎市産業振興会館で開催された「終活フェア」には約400人の市民が集まり、この様子がフジサンケイビジネスアイに掲載されている。 これは「神奈川終活フェア実行委員会」という葬儀社、士業ネットワーク、保険会社、介護事業者、遺影制作会社などの異業種が連携して作られた組織が主催したものである。 当日は遺言から医療、介護、相続、墓をどうするかということまで相談を請け負う専門家や業者が集まり、各団体、企業による企画展示なども行われたようだ。 人生の最期をテーマにするイベントなだけに、暗い雰囲気で敬遠されないように、明るい雰囲気の中で死について考える環境づくりを試みたようで、 来場者が実際に棺の中に入る入館体験や、祭壇に飾られた遺影の枠から会場を眺めることができる体験コーナーも設けられていたようだ。 このように終活イベントが賑わう中でその大きな位置を占め、注目されているのがエンディングノートである。 全国で葬祭ディレクターなどによる「エンディングノートの書き方講座」の開催も盛んである。
2.2 エンディングノートと生前予約システムについて
エンディングノートとは、死後の手続きや家族に伝えたいことを書き留めるものである。 書店で販売されているのを見かけることも多くなり、終活フェアなどで配っている自分が生まれ育った環境から現在に至るまでの自分史、介護や終末医療についての希望、財産や相続について細かく記載できるようになっている。 その中でも自分が望む葬儀の形を記載するページは多くを占めているノートが多い。葬儀をするか否かの選択から始まり、葬儀を託す人、費用、葬儀社や会場、宗教、式の内容、墓にいたるまで記載する欄が設けられている。 エンディングノートには遺言とは違い、法的拘束力はない。対して死後の事務手続きや葬儀に至るまで法的拘束力を持って事前に決定できるのが生前予約システムと呼ばれるものである。 これはアメリカのプレニードフューネラルアレンジメント(葬儀の生前準備)から影響を受けて、10年ほど前から日本にも台頭してきたシステムである。 アメリカでは日本よりも離婚率が高いため、葬儀の担い手がいない人が多く、葬祭業者の98%がプレニードのシステムを採用している。 これは本人が生前に自分の葬儀内容と費用の支払い方法などを決め、葬祭業者と契約を結び、自分の死後に契約先から派遣される人物が、死後の事務処理や葬儀の準備まですべて行ってくれるというサービスである。 日本ではLiSSシステム(Living Support Systemの略)が1993年に発足され、株式会社としてスタートし、2000年からNPO法人となっている。同年にはウィルバンクという同様のサービス内容の株式会社も立ち上がる。
これらのサービスとエンディングノートは死期に備えるという点では同じ目的をもったものであるが、実際の働きは異なるといえるだろう。 エンディングノートは自分の意向を家族に伝えるものであるが、生前予約システムは本来、自分の死後、自分を送ってくれる家族がいない単身者や、身内に頼れない人の需要に答えるかたちで台頭してきたサービスといえるだろう。 ウィルバンクは家族をもっている人しか会員となれないコースが主流であり、葬儀に関する生前の意思を預かり、それを実現することを主な目的としているが、実際には単身者向けに、死後の事務処理や葬儀を取り仕切るサービスも行っている。 LiSSシステムはというと、その前身は「もやいの会」というすがも平和霊苑の会員勉強会であった。] この霊苑は跡継ぎのいない人の遺骨の埋蔵が可能であり、血縁によらない新しい墳墓形式として注目された合祀墓のある霊苑である。 お墓は決まったが、その前の葬儀はどうしたらよいか、という会員の心配に答える形で構想されたのがこのLiSSシステムなのだ。
以下はホームページに記載されている趣旨書の引用である。
新しくスタートする葬儀の生前契約は、自分の葬儀を自分自身が生前に企画し、参列者、式場、葬儀の方法、宗教儀礼、会葬者への返礼、死後の供養に至るまでを、会員と当システムの間で、契約の締結をしておくものです。 この契約を結ぶことにより、一人暮らしの人や、遺った家族に迷惑をかけたくないと思っている人々の心配をなくし、残りの人生をより豊かに過ごしていただければと考えております。
引用文中にある、「家族に迷惑をかけたくないと思っている人々」はキーワードとなる。
2.3 終活ブームの背景と二つの局面
2章で上述してきたように、現在「終活」という言葉はかなり一般化し、出版本も多く、メディアを賑わせている。 以前は死にまつわる葬儀の話題は縁起が悪いとタブー視され、現在のようにテレビで扱われることも無かった。 葬儀は遺されたものがするものだという観念が強かったこともある。 ところが、1.3で述べたように、高齢社会の進展や、医療の進歩によって死の予告が可能となったことにより、誰もが「死」を考えざるを得ない事態を迎えているといえる。 自らの死、および死後について、かつては残る家族に託すことができた。それが今は託せなくなったことが、死、死後について関心を持たざるを得なくなった大きな理由だと言える。 また、1.3でも家制度の崩壊について少し述べたが、家制度の重要な柱の一つとして「先祖祭祀」があった。 これは、自分の先祖の葬儀や年忌抱法要や仏壇、墓の世話などの祭祀を、生きているうちに自分が行うことが、自分の死後、子供や孫が自分のために祭祀をしてくれるという保証になるというものであった。 しかし、現在都心に住んでいる高齢者の世代は、若いころ高度経済成長の時代に田舎から都会へ出てきて、核家族を作り、自身は先祖祭祀に参加していないケースが多い。 そのため、自分の祭祀を子どもに任せることを「迷惑をかける」などというように感じるのだろう。
以下は私自身が終活セミナーへ参加し、参加者に話を聞いた印象である。 葬儀の事前準備をする高齢者のその主な動機は「子供に迷惑をかけたくない」というものが1番にあると感じた。 私がセミナーに参加した理由をうかがうと、実際に終活セミナーなどへ参加される方は、自分がいずれ死ぬことはわかっていても、まだ死を遠くに感じている人が多い。 60代の方が多く、参加者の親も健在で、自分の最期を見据えてというよりも、親の万が一の時に焦らないようにという理由から参加される方も多かった。 女性も男性も60過ぎくらいの参加者は、60歳まで働いており、セカンドライフを豊かにするための一環として、地域でこのようなセミナーがあったから参加した、と話してくださる人もいた。 自分がまだ元気であるがゆえに、子供に頼りたくない、自分が動けるうちになるべく自分で準備をしておこうという思いが強いのではないか。 「終活」に前向きに取り組める人は、まだ自分の死を遠くに感じている人々だ。だからこそ落ち着いてこれからの人生を再考することができるのだろう。
もともと終活という言葉が世に出てきた要因としては、高齢化社会、核家族化による血縁関係や地域共同体の崩壊などの社会的要因から、自分の死について考えざるを得ないという状況が生んだものだったと言える。 しかし、転じてセカンドライフを豊かにするための契機として、エンディングノートや終活セミナーが用いられている面もある。 最期を見据えることから自分の人生を振り返り、残りのセカンドライフを自分らしく生きようという積極的な姿勢を生んでいるという点では、終活ブームの到来は評価されている。
3章 「よい葬儀」とは何かを考える
3.1 葬儀の意義
1章2章で、現在の葬儀事情やそれにともなう終活ブームについて述べてきた。 これを踏まえて現在においての「よい葬儀のあり方」を考えるために、まず葬儀の意義を考えてみたいと思う。
葬制研究者である山田は、葬送儀礼とは死を物理的、文化的、社会的に「変換」する儀礼だというように述べている。(山田、2007) 死の物理的転換とは、現在の日本でいえば火葬である。 遺体が火葬され、遺骨となり、物理的な変換がおきる。これは言わずもがな葬送儀礼の中心である。死の文化的変換とは、死者の存在形態の変換、移行を指す。 日本においては、人は死ぬとホトケになるという考え、文化をもっているため、葬儀、その後の追善供養を経て「ホトケ」に位置付けられていく。 残された者については、死者が担っていた社会的役割を残された者に託し、社会関係を再編成することになる。これが死の社会的変換である。
上記は葬制研究上のカテゴリー分けであるので、死者を送る遺族にとって葬儀がそのような意味を持つかに話を落として考える。
死の物理的、文化的、社会的変換を言い換えれば、死を確認し、死を受け入れ、故人の縁者、世間に死を知らせる、ということになるであろう。 ここに葬儀の意義は集約されるといえる。 現在は葬儀社に任されることがほとんどであるが、本来、通夜の後、翌日の告別式まで線香を絶やさず一晩遺体とともに過ごすという過程があった。 ここで家族は故人と最後の別れができ、死を確認できるのだ。 現在は様々な形をとっているが、通夜の翌日に行われる告別式は会葬者の焼香がメインである。 世間や故人の縁者に死を知らせ、生きている人間が故人に別れを告げるための式典である。そこで私が考えるのは、この3点を葬儀の本質、意義であると考えた場合、この20年の葬儀のあり方の変化は、見直されるべきだということだ。
3.2 葬儀のあり方の急速な変化への考察
・3.2.1 葬儀の簡素化、低価格化について
1.1.1では、新しい葬儀のあり方として、都心では家族葬が主流になってきており、一日葬や直葬というものまで出てきたと述べた。 『小さなお葬式』というブランド名で、インターネットから受付をできる葬儀社まであり、その葬儀社では火葬をメインにした一日葬が依頼率の50%をも占めているという。 こうしたサービスは、社会の変化に応じて、「消費者のニーズによって」生まれてきたサービスかもしれない。 読売新聞のアンケート調査では、「最近、通夜や告別式を行わずに、火葬だけをする「直葬」が行われています。こうしたやりかたをどう思いますか。」という問いに対し、「とくに問題ない」と回答した人の割合が72%にも及んでいるというデータもある。 葬儀社も一企業であるので当然と言えば当然の動きである。しかし、こういった世間のニーズに答えるという葬儀社の動きが、葬儀を簡素化させ、それを世間がよしとする傾向に拍車をかけているといえる。 では、葬儀の「簡素化」は悪いことなのだろうか。前述した「葬儀についてのアンケート」で「自分自身の望ましい葬儀のかたち」という問いでは、 「人生最後のセレモニーにふさわしく、立派な葬儀にしてほしい」と回答した人は2.3%にとどまり、「費用をかけないでほしい」と回答した人の割合が最も多く63.2%であった。
そもそもこのようにアンケート調査などで使われる「簡素化」という言葉は、従来の葬儀に比べて簡素という意味であろう。 アンケートの回答者にとって「簡素な葬儀」は一律ではなく、実際には現在の葬儀の全国平均額以上の費用をかけた葬儀を想定している人もいるだろう。 また、仏具にだけ良いものを用いて食事にはお金をかけない、であるとか、装飾は控えめに、しかし戒名は先祖と揃えて位の高い者をつけてもらうなど、何を派手で豪華であるとするかは人によってまったく見識が異なる。
しかし、回答者が「簡素」と聞いて比較対象として想定するのは、高度経済成長期以降、華美になり、大規模化した葬儀のことであろう。 このように大規模な葬儀がなぜよく思われなくなってきたかと言えば、義理で参列する者が多い、世間への見栄で高額な費用を使うことになる、葬儀の立派さが、故人の生前の業績を表しているかのような風潮があったからであろう。 参列者が多ければそれだけ、通夜振る舞いや精進落としの接待などの遺族の負担は金銭面でも、時間、労力の面でも大きくなる。 そのため、遺族は準備に追われ、故人をゆっくり偲び、悲しむ時間も持てなくなる。 そのような事態を見直しての「簡素がいい」ということなのだろう。 家族とゆっくりお別れをしたいという思いから、家族葬が一般的になってきたことも納得できる。
しかし、参列者を近親者のみと限定し、葬儀社の段取りに従って合理的に進め、手間を省くことが、遺族が故人をゆっくり偲ぶことにつながるのだろうか。 自宅で死を迎えることが減少し、それに伴って葬儀の場所も自宅から斎場へと変化した。このことは以前よりも、葬儀社の段取りに従い、ただ与えられた工程をこなすだけという「形骸化」につながっているといえないだろうか。 葬儀のあり方が見直され、葬儀を上げる際の遺族の負担は減り、小規模で近親者のみの葬儀は一見、故人をゆっくり偲ぶことができるかのように思われる。 しかしそれは形が変わっただけで新たな葬儀の形骸化なのではないだろうか。 葬儀をあげる遺族が、「簡素な葬儀でなるべく手間をかけずに」とは思っておらずとも、葬儀社に依頼し、段取り通りに葬儀を進めることで「これでよかったのだろうか」という思いが残ることもあるだろう。 消費者に求められている価格の明瞭化、葬儀の小規模化に答える葬儀の形などとともに、競うように低価格化を進めている葬儀社業界の動向は、もっと危惧されるべき事態であろう。
・3.2.2 仏教と葬儀について
1.2では、無宗教葬という選択肢がでてきたこと、実際に無宗教葬で葬儀が行われている件数はまだ少ないものの、宗教に依らずに葬儀をあげたいと思っている人が増えてきていることを述べた。 葬儀にかける費用は減少傾向にあるものの、その減少分の多くは葬儀社に支払う額であり、寺院に支払うお布施代の相場が下がっているとは考えにくい。 私が本研究を始める研究動機にもなった通り、世間的にはお布施を高額だと感じ、合点のいかない戒名料に対して不満を抱いている声が多いと言える。 「葬儀についてのアンケート調査」では、葬儀費用のうち、寺院に支払った費用の全国平均額は51.4万円となっている。 しかし回答は、1万円から188.8万円とかなりの開きがあったようだ。同アンケート調査の3年前のものでは、最高額で250万円という回答もあった。お布施の額を高いのか、妥当な額なのか判断する基準は難しい。 このような寺院へ支払う費用の不透明さへの不満から、明瞭化が求められてきている。
これは、繰り返し述べてきているように、都市化によって檀家制度が形骸化、あるいは崩壊が大きな原因となっている。 従来、檀家制度は寺と檀信徒との間に、何世代もの付き合いがあるという信頼関係のもとに成り立っていた。僧侶も地域の住民のことをよく知っていて、縁のある者の死に対してお経を読んでいたのだ。 寺が地域の葬儀を請け負い、墓を守ってくれているので、檀信徒も(お布施というかたちで)寺を守ろうという意識があった。しかし、現在都市部においてこのような信頼関係はほとんどなくなってきていると言ってよいだろう。 墓は田舎にはあるが、寺の宗派すらわかっていないという人も中にはいる。よって寺とは日頃付き合いがなく、面識のある僧侶も到底いないという訳で、僧侶に葬儀でお経を読んでもらうことに対して、ただの「消費者」になっている人が多いのだ。 消費者目線なので、価格の明瞭化を求め、不当に高額であるというような考え方になるのだろう。しかし実際は全国の寺の経営状況は悪化し、現在の収入だけでは維持が難しくなってきている寺も多い。 地方では都市への人口の流出によって葬儀の数、檀家の数自体が減っているし、年忌法要も減ってきている。 初七日、四十九日、百か日、一周忌、三周忌、七周忌、十三周忌ときて、三十三周忌で弔い上げという習俗によって、故人が先祖神として祈願の対象として神格化されるという考え方、文化があり法事が行われることになるが、 子どもが親の三十三回忌まで生きていられることはまれである。 初七日は葬儀と一緒に済ませるのが一般的であるし、年忌法要を寺に頼んで行う期間、回数も減っているのが現状だ。 そうなれば、当然寺の維持も難しくなる。檀家制度の崩壊によって、葬儀社が寺を紹介するという形が普及する。 そして、最近では、料金の明瞭化を謳って全国一律料金で僧侶を派遣してもらえるシステムまで登場している。 このような僧侶派遣システムで「出稼ぎ」をおこなう僧侶も出てくるのだ。
このような事態を葬送ジャーナリストである碑文谷は厳しくみており、見直されるべきであると述べている。 (碑文谷、1994) 私もこの考えに賛同したい。墓を永年維持してくれていると考えれば、お布施額は決してぼったくり価格ではないというのが私の意見だ。
このような現状を招いている理由として、社会的変化に伴った対応が寺、僧侶側になかったことも考えられるだろう。 寺がどういった役割を果たし、葬儀での読経にどのような意味があるのか、私たちがわからないのであれば説明する責任があるだろうと思う。 同時に、私たち「消費者」も、お布施をただ不当に高い、いくらかかるのかわからないと言って不満を漏らすのではなく、自ら知ろうとする姿勢が必要だ。 お布施は平均としては相場があっても、寺に直接相談し、家庭の事情によって金額を考慮してもらうこともできるのだ。 無理に院号をつけて、支払えないような高額な戒名料を請求してくるのであれば、別の信頼できる寺に頼ればよい。 一部、利益に執着する僧侶がいることは事実で、この一部によって寺全体に対して不信感が広がってきたのだ。 信頼できる僧侶を見つけ、僧侶と話をすることで、お布施、葬儀で読経してもらうことの意味を解し、納得してお布施を渡すこともできるだろう。
付き合いのある菩提寺がない場合、生前から信頼できる寺、僧侶を探しておくことが必要となると思われる。 いざ家族が亡くなってからでは自分で僧侶を探しているような余裕はない。 そのため葬儀社に紹介されるまま、金額を提示されるまま納得がいかず「高くついた」と感じてしまう事態に陥ってしまうのだ。 この点から考えれば、葬儀について事前に考え、準備する傾向はよいといえるだろう。
次に、アンケート調査では「自分の葬儀は宗教色のない葬儀にしてほしい」と回答する人は多く、その他葬儀事情は大きく変化し、自由化が進んでいるにもかかわらず、無宗教葬が現状普及していないかを考える。
その理由を4点にわけてみてみることにする。ひとつには、無宗教葬にしてしまうと、何をすればよいのかわからないということにあるだろう。前例が少ないため、すべてを自分で決めなくてはならない。 よって故人が生前によほど準備していない限り、遺族の意思だけで無宗教葬を選ぶということにはなりにくい。 アンケート調査はあくまでも「自分の葬儀」の場合の問いであり、自分が遺族となって葬儀をあげる場合はこの回答の限りではないだろう。よって故人の遺志が大前提となっているといえる。
ふたつ目は、「成仏できない」という意識である。これは日頃、自分自身を信仰心が全くないと考えている人にも当てはまるといえる。 人が死んだら、あの世へ逝き、成仏するという考え方は特定の宗教、宗派に属しているか否かには関わらず、日本古来からの慣習、文化として現代の私たちに根付いている考え方なのではないか。 文化人類学者として葬制研究を行っていた内堀基光は、彼の著書の中で以下のように述べている。
日常は仏教徒と意識していなくとも葬儀を仏式で行っている人々は、それを前向きの葬儀の儀礼として意識していないかもしれない。 しかし逆にとらえ、もし一切の儀礼をおこなわなかったらどうなるかと問えば、死者が「うかばれない」とか「成仏しない」という人は少なくはないだろう。(内堀、1997、89-91)
内堀は死者の表象とかかわる儀礼を二分し、「前向き」「後ろ向き」の儀礼と呼んでいる。「 前向き」とは、儀礼の執行が死者の存在形態を別の存在形態へと変える(移行させる)意図のもとになされることを意味する。3,1で記述した、山田の述べている文化的変換に相当すると考えられる。 「後ろ向き」とは死者の生前の功績を称揚するという意図が葬礼の中で表明されていることを指している。無宗教葬は、死者を仏にするための儀礼ではないので、「後ろ向き」な儀礼ということができる。 敬虔な仏教徒や先祖崇拝の気持ちが強い人でない限り、日頃から先祖は仏であり、葬儀は死者を仏へと変換させる儀礼だとは考えていないだろう。 しかし、無宗教葬のように一切の宗教儀礼をなくしてしまったら、「成仏できないのではないか」というように感じるものなのである。
3つ目は、無宗教葬への物足りなさとでもいうべきものである。 死という大きな非日常性に対して、宗教性は大きく機能してきており、日頃意識せずとも日常を超越したものに縋りたいというおもいが働くものなのではないだろうか。 鎮魂、遺族のこころの鎮静として本来読経は機能しているのである。 無宗教葬では、葬儀が日常の延長にしかなりえないのではないか、というもの足りなさが働いているといえる。
4つ目は、本人や遺族が無宗教葬を望んでいたとしても、親戚に反対されたり、参列者が望んでいるかたちを考えて、いわゆる「普通の」仏式葬を選ぶという場合がほとんどだからである。 例えば、現在の現役で働いているような世代の人々であれば、私の親のように「葬式に僧侶はいらない」とはっきり意見をもっているような人も多くなってきているだろう。 しかし、現在の高齢者にはそのような考えをもっている人は少ない。よって高齢で亡くなられた方の葬儀に集まる高齢の参列者の中には、無宗教葬であることに対して違和感や不安感を抱く人のほうが多いと考えられる。 そのような人を無視して、故人の遺志を貫くことが良いことなのかどうか、なかなか自信が持てないだろう。
無宗教葬の普及が進んでいないことの理由から、4つめにあげた「葬儀は誰のためのものか」という疑問が生じた。この点について考えてみたいと思う。
3.3 葬儀は誰のためのものか―終活にみる「送り手」の不在―
死者、遺族、故人の縁者とよい葬儀について考える視点はそれぞれ異なる。現状として、高齢者、親世代の人々は「子供に迷惑をかけたくない」と思っている人が多い。 また、家族だけで送って欲しいと希望していて、遺族が故人の遺志をそのままに密葬という形で葬儀を上げたとすれば、 故人と親しかった人々の、故人との別れの場を奪うことになる。3.2.1で前述した無宗教葬についても、参列者が快く思わない要素があるのであればよい葬儀であったとはいえないだろう。 では「送る側」である子どもとしてはどうであろうか。簡素でいい、と言われてそのまま「そうですか」と簡素に済まそうとすることは出来ないはずである。 立派にお金をかけた葬儀が親の生前を象徴し、故人を偲ぶことでは無いとわかっていても、生前の感謝の意を何らかの形にして表したいという気持ちが働くだろう。 3.1で前述したとおり、今は葬儀の進行自体は葬儀社に委ねられ、労力は軽減されていることから、何かしたいと思っても出来ないということも考えられる。 2.3では、終活ブームが自分の最期を見据えることで、残りのセカンドライフを豊かにしようという積極的な姿勢のきっかけとなっている点ではよいことだというように述べた。 世間でもこのような評価がされているといえる。しかし、自分で自分の「死に支度」をこれだけ積極的にするような時代はかつて無く、もっと慎重にこの状況を考えてみる必要があるのではないだろうか。 実際に親の葬儀をする子どもは、親の老後、葬儀の希望を聞くことなく、まかせっきりにしてしまってよいのだろうか。
このように、故人、葬儀をあげる遺族、参列者との希望や思いが複雑に絡んでいるのが難しい点であるが、 ここではあえて、葬儀は送り手である遺族のためにあるものであると考えたい。 終活など、自分の死を自分で準備するという考え方が出てきた今、葬儀の送り手の存在を改めて重視することがひつようなのではないだろうか。 故人の生前の希望やエンディングノートの記述は、遺族が「故人が望んでいた形を実現できた」と納得のできる材料として位置付ければよいだろう。
今回「よい葬儀」を考える上で、対象は子どもが親を送る葬儀の場合を想定して考える。 地域のつながりが薄れ、親戚との関係や葬儀への参列も少なくなってくると考えられる中で、 親子関係はたとえ会うことが少なくなったとしても、切れない縁であり、変わることのない絶対のものである。 子が親の最期を考え、よい葬儀をと考えることから、葬儀が小規模化し、遺族の負担が減ってきている現状での、新たな形骸化の流れを止めたいと考える。
3.4 葬儀の個人化を受けて―故人らしさの演出―
この節からは、上述してきた葬儀のありかたの変化や、葬儀の事前準備に関心が集まってきてはいるものの、 そこに「送り手」の存在がみえないことを踏まえて、子が親を送る葬儀で、遺族である子どもが「よい葬儀であった」と納得できるような葬儀を考えていこうと思う。
そこで私が提案したいのが、「故人の人柄がわかる、故人らしい葬儀」だ。「らしい」とはあくまでも故人の人柄が出ているという意味で、 故人が生前に一般的でなるべく小さな葬儀をと考えていたとしても、それをそのまま受け取る必要はない。 1章で述べたように、葬儀は「個人化」し、従うべき規範がなくなっている。これを積極的に捉え、もっと葬儀を故人らしく演出する。 葬儀を、故人を中心とした思い出を共有できる場として機能させることで、遺族の悲しみを癒す助けになるのではないかと考える。 そして、遺族は故人の希望にかかわらず、故人と親しい付き合いのあった人は参列者として招いた方が、その場の労力は大きいかもしれないが結果として、よい葬儀だったと思えるのではないだろうかと考える。
「葬儀についてのアンケート調査」の「感動を覚えた葬儀」という問いの回答を参考にしてみよう。 「参列者の葬儀に感動した経験はあるか」という問いに対し、30.7%の人が「ある」と回答している。 記述部分では、スナップ写真が飾られていたこと、写真をスクリーンに映し出され、故人の生前の様子を思い出したこと、故人の趣味、思い出のものが展示されていたこと、故人の好きだった歌を流していたこと、などが記述されており、 故人の生き方や人柄が表れていたことに対して感動したと感じる人が多いようだ。感動を覚えさせる葬儀がそのまま「よい葬儀」だというわけではない。 しかし参列者が故人の思い出に触れることで、感動したと感じるということは、形式的に葬儀が過ぎ去ってしまうよりは、参列者に故人の記憶を残し、より死を悼むことができるということなのではないだろうか。 遺族にとってもそのことは救いとなるはずである。 さらに、故人らしさを演出し故人の縁者が揃った場で、お互いが知らなかった故人の面を知ることにもなるだろう。 遺族の知らない故人、他の参列者の知らない故人をお互いが共有する場として、葬儀は二度とないと言ってもよい機会である。
故人が「子どもに迷惑をかけたくないから」という理由で葬儀の事前準備や終活を行うことは歴史的に見ても異常な事態である。 「迷惑をかけたくない」と願うよりも、自分の生前の意思や考え方、生き方などを少しでも多く子どもに伝え、親孝行させることが結果的には子どもが親を亡くした時の悼みは、後悔なく癒えていくのではないだろうか。
3.5 故人らしさを演出した葬儀の場合に考えられる問題点
故人らしさを演出した葬儀を考える場合、問題になってくる点が2点考えられる。1点目は「故人らしい」と言っても、故人にとっての自分らしさなのか、遺族にとっての親らしさなのかによっても演出方法は異なってくるということである。 「自分葬」の「自分」は、死を見据えている側のことである。よって私が提案したい故人らしい葬儀とは、「自分葬」と呼ばれるものとは異なるとも言える。 たとえば、葬儀社がホームページで紹介していたり、メディアでとりあげられるような「自分葬」には、最近の葬儀の傾向に反して派手で大規模なものが多いと感じる。 焼香の変わりに故人の好きだったワインを献杯するワイン葬は、参列者の数が多ければその分費用も高くつく。 自分らしい葬儀を、と準備する段階でこのような情報を目にし、華美になることは避けるべきだろう。 そもそも葬儀にいくらかけられるか、という問題は家庭の経済状況や価値観により、葬儀費用についても各家庭が判断するところとなり「個人化」されているので、事前に自分らしい葬儀を考えようとすると、 費用から考えなくてはならなくなってしまうように思われるかもしれない。 しかし、「自分葬」という特別なものにしようという意識は不要である。 思い出の品を飾る、好きだった音楽をかける、スナップ写真を飾るといった程度であっても、それを準備するためにかけた時間はいちばんの死者への弔いになるのではないだろうか。
自分らしさを自分で決め葬儀内容をも自分で決めて、生前予約システムで契約したり、エンディングノートに記すだけということは避けるべきである。 当人が避けるべきという訳ではなく、子どもの側からの働きかけが大事なのではないかと考える。 子が親を亡くし、遺族となった時に、葬儀に参列してくれる人に対して親がどのような人物であったか、子にとって親がどのような存在であったかがわかるような演出方法を、子どもが考えていくべきなのだ。 そのためには、生前から親の考える自分らしさと、子の思う親らしさ、そしてその中のなにを参列者と共有したいのかをすり合わせることが大切であろう。
考えられる問題点として2点目は、3.2.2で述べた無宗教葬が普及していない理由に「日常の延長となってしまう」ということをあげたが、これがこのまま当てはまるだろう。 家族と親しい参列者の間で、緊張感がなくなり、儀式としての厳かさに欠ける事態を引き起こしかねない。 これは死の儀礼としては避けるべきことだと考える。縛りとなる規範が薄くなり葬儀の個人化が進んだことを積極的に捉えて、故人らしさを演出した葬儀がよいのではないかという主張であるが、葬儀の間、どこからどこまでその演出を行えばよいだろうか。 「らしさ」に囚われすぎて、無宗教葬でなければならないとか、なるべく慣習に従われずに、などと考えることはよくない。死の儀礼としての厳格さ、非日常性は簡単に取り払うべきではないだろう。 「自分の葬儀は明るい雰囲気でパーティーのようにして欲しい」という希望も聞くが、そのようなかたちをとったとしても、30分でも厳粛に、遺体を前にして故人と向き合う時間が必要だと考える。結婚式のような感動演出になってならない。 ではどうするか。私は日本の仏式葬の慣習を残していくべきだと考える。 決して仏式葬というかたちをすすめているのではない。故人が強く無宗教葬を望んでおり、遺族もそうしたいと考えているのであれば、その家庭にとっては無宗教葬がよい葬儀ということになる。
しかし、3.2.2で述べたとおり、日頃死んだら仏になるというような思想を持ち合わせていなくとも、家族が亡くなり悲しみにくれている時にそのような考え方はひとつの助けとなるし、 僧侶は本来そのような教えを庶民に伝え、遺族の悲しみを癒す役割があったはずである。そのような信頼関係が薄くなった今、その信頼を取り戻すことは難しいだろう。それでも誠意をもって遺族のため、故人のために読経をする僧侶もいる。 読経の間、厳かに式が執り行われることは死の儀礼としての非日常性を保つために必要な時間なのではないだろうか。 寺や僧侶が葬儀の仏教離れをもっと危惧し、世間に受け入れられる方法を考えなくてならない時なのではないだろうか。
序論で、葬儀と告別式の違いについて述べたが、現在の「葬式」は、死者の弔いを目的とした宗教儀礼である葬儀式の地位が低下し、社会的儀礼である告別式が主流になってきているといえる。 故人らしさを演出するということは、社会に向けて、という要素が強い。家族だけであれば、あえて演出する必要などないのだ。社会に向けた告別式に重点ををくことで、葬儀の本来の意義である故人への弔いの時間をなくしてしまっては意味がない。 そのために宗教儀礼である葬儀式、僧侶に読経を依頼することは残されていくべき文化なのではないかと考える。
自らの葬儀を考え、無宗教葬を望んでいる人々は、世代的にまだ無宗教葬を経験していない人がほとんどいないと言ってよいだろう。 つまり、「無宗教葬がよい」というよりは、「仏式葬に問題がある」という見方をしていると言った方が正しいのである。無宗教葬を経験していなければ、そこにまつわる問題点は見えてこない。 自分の葬儀を考える際、従来の仏式葬のイメージや、寺、僧侶の偏見だけで無宗教葬を安易に望むのではなく、なぜ自分がそのように望むのか考えてみることも大切である。
また、故人と遺族の意見が食い違っている場合や、参列者に無宗教葬に反対する者、快く思わない人がいるであろうと考えられる場合は、 故人の遺志ではなく生者がどう故人を送りたいか、どのような形をとれば遺族と参列者がゆっくりと故人を偲べるかを優先させるべきである。
僧侶の宗教者としての現状の改革と、私たち「消費者」となってしまった者の意識の変革が必要なのではないだろうか。
結論
以上、「よい葬儀」とは何かを考えるために、この15年から20年の間に急激に変わってきた葬儀事情や、「終活」の流行を調査、分析してきた。
死を確認し、死を受け入れ、故人の縁者に死を知らせるという葬儀の意義からすると、この20年の葬儀のあり方の変化は見直されるべきであると考える。 自分自身の望ましい葬儀の形を問うアンケート調査では、簡素に余計な費用をかけずに行って欲しいと願う人が多かった。また、次いで多かったのが家族だけでゆっくりとお別れをしたいという回答であった。 高度経済成長期以降の、立派で大きな葬儀ほどよいという考え方によって形骸化された葬儀への反省と、「自分の子どもには経済的負担や迷惑をかけたくない」という思いを持った人が増えてきていることを表しているだろう。 このような社会のニーズに葬儀社が答え、一日葬や火葬をメインとした葬儀が低価格でできるプランが出てきた。 しかしこのように簡略化され、合理化された葬儀は、実際に送る側が求めているものなのだろうか。
故人の遺志を反映させることがよい葬儀なのではない。遺族が、しっかりと故人を偲ぶことこそが大切であると考える。 その方法のひとつとして、「故人らしさ」を反映させた葬儀があるのではないだろうか。 単に故人による「自分葬」ではなく、遺族から見た故人や生前の人柄、故人の好きだったことなどを参列者と共有し、また参列者と遺族が故人を思い語り合う機会として葬儀を利用するのである。 遺族は生前知らなかった故人を垣間見ることができ、参列者にとっても同じだろう。このことは、すぐには叶わずとも気持ちの整理をつけるうえで有効なのではないだろうか。
そのためにはやはり事前の準備が必要であろう。送り手がもっと葬儀に関して関心を持つべきだ。 これはエンディングノートを記載する、葬儀社を探すという具体的な準備だけを意味しているのではない。
子どもが、親が葬儀に対してどのような考えで、どのような希望をもっているか早くから問うことが必要だ。 その意思を反映させるかどうかは別として、親の希望を知っておくことは子どもが納得して葬儀をあげるために必要なことであるからである。 葬儀のかたちが多様化し、コンセンサスがなくなってきている今、親子間でろう死や、死後に対する考え方は異なるだろう。 これから葬儀をあげる送り手は多様化した選択肢の中から葬儀のかたちを自分で決めなけらばならないところまで来ている。
送られる側と送る側で考え方の祖語が生じやすいのが、1.2で自分らしい葬儀のひとつとしてあげた、海洋葬や樹木葬と言われる散骨であろう。 自分の死後を考えた場合、散骨を希望する人は今後増えてくるだろう。しかし家族が亡くなったら、家族の骨は散骨したいと積極的に考えている人はいるだろうか考えてみて欲しい。 お墓もなく、仏壇も設けず、遺骨も手元になかったとしたらどうだろうか。 家族が亡くなって葬儀も終わって落ち着いたときに、手を合わせる対象がないことは遺族にとって不安となるだろう。 年忌法要やお墓参りにあたるものはどうすればよいのか。遺族にとって長く迷いが生じることとなるのだ。
葬儀の場所はどうするのか、葬儀社に依頼して行われる仏式でよいのか、無宗教葬を選ぶのか、遺骨、墓はどうするか、考えなくてはならない点は数多くある。 これらを生前に親子で話し合ってみることで、お互いに新たな考え方を知ることもできるだろう。
そしてその働きかけは、親が元気なうちに、なるべくはやくから行うべきだ。 終活セミナーに積極的に参加していた人々が、まだ自分の死を身近に感じていない元気な人々が多かったように、死を身近に感じていないからこそ落ち着いてゆっくり取り組めるのだ。 自分の死について考えること、準備することへの忌避感は終活ブームに見る通り薄くなってきている。しかしこれはあくまでも自分の死に対する準備だからであって、自分以外の家族に対してであると、途端に話を切り出しにくくなるだろう。 だからこそ、死を日常で感じない元気なうちに、将来送り手となる子どもの側から親への問いかけが、大きな意味をもつのではないだろうか。そしてそれは学生のうち、結婚前であれば尚実現しやすいのではないだろうか。 親に扶養してもらっているうち、親が子どもをまだ自分が守るべき存在だと考えているうちであれば、葬儀の話もしやすいだろう。 もちろんその時の考えと、年を取ってからの考え方とではまた異なってくるかもしれない。 しかし一度でも葬儀についての考え方を聞いておけば、数年後も話をできる機会が来るだろう。
親が「子どもに迷惑をかけたくない」と思いそのニーズに答えた葬儀社のプランが主流となる中で、 送り手となる側は送り手となる側で、どういった葬儀をあげればしっかり故人を偲ぶことができるのか考えるべきであると考える。故人が散骨を望んでいるのなら、事前に調べてみて自分がそれを受け入れられるか考える必要がある。
おそらく、葬儀社がこのまま世の中のニーズに答えるような葬儀を展開すれば、葬儀の形骸化は止まらないだろう。斎場で葬儀社の仕切りによって行われる葬儀が一般的になった今、 送り手がそれを望んでいなくとも、あっという間に葬儀が終わってしまった、という事態になりかねない。
葬儀社の進行とは別のところで、故人らしさを演出する葬儀を行うことにより、この事態は避けられるのではないだろうか。 思い出の品を飾る、好きだった音楽をかける、スナップ写真を飾るといった程度であっても、それを準備するためにかけた時間はいちばんの死者への弔いかたなのではないだろうか。
参考資料
財団法人 日本消費者協会 第9回「葬儀についてのアンケート調査」報告書2010年11月
読売新聞社「冠婚葬祭」世論調査 2012年2~3月実施 2012年04月07日 読売新聞 東京朝刊
フジサンケイビジネスアイ Fuji Sankei Business i. 2012年11月23日
参考URL
参考文献
碑文谷創『「お葬式」の学び方』講談社 1994
碑文谷創『生前から考え、準備しておく 自分らしい葬儀』小学館、1998
山田慎也『現代日本の死と葬儀 葬祭業の発展と死生観の変容』東京大学出版会、2007
藤井正雄『現代人の死生観と葬儀』岩田書院、2010
島田裕巳『葬式は、要らない』幻冬舎新書、2010
ひろさちや『お葬式をどうするか―日本人の宗教と習俗―』PHP新書、2000
勝田至 『日本葬制史』吉川弘文館 2012
近藤功行・小松和彦 編著 『死の技法 在宅死に見る葬の礼節・死生観』ミネルヴァ書房 2008
内堀基光 1997「死にゆくものへの儀礼」青木保ほか編 『儀礼とパフォーマンス』岩波書店
葬送の自由をすすめる会『<墓>からの自由』社会評論社