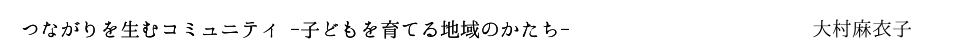
目次
序論 高校生における自己肯定感の欠如
第一章 地域コミュニティの現状
第一節 コミュニティに関する人々の意識変化
第二節 現在の人と人との関わり
第三節 地域コミュニティという定義
第二章 コミュニティ活動の現状
第一節 活性化するテーマコミュニティ
第二節 ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスの台頭
第三節 地域の人と人とをつなぐコミュニティ
第三章 子どもと地域をつなぐコミュニティ
第一節 高校生を取り巻く他者との関係性
第二節 子どもに対する地域という他者
第三節 地域コミュニティ活動による高校生へのアプローチ
結論 地域コミュニティと自己肯定感
参考文献一覧
序論 現代の高校生における自己肯定感の欠如
2011年3月、財団法人日本青少年研究所による調査結果が発表された。 「高校生の心と体に関する調査」※1は、日本の地域別に10県を選択し、計10校(各県一校ずつ)にアンケート調査を行ったものである。 質問項目は大きく分けて8つのカテゴリーに分類される。運動、体型とダイエット、食事と睡眠、喫煙と飲酒の経験、健康と衛生に関する態度、情緒とストレス、自分の性格調査と自己意識、そして他者との関係性である。 この調査は、2010年9月から11月にかけて行われた。 同じ期間に同じ手法を用いてアメリカ、中国、韓国でもアンケートを実施し、結果を比較している。
このアンケート結果は、現代の高校生像を知る手がかりとして様々な場面で引用されている。 その中でも注目すべきは、次の質問事項だ。「私は価値がある人間だと思う」という質問に対し、「全くそのとおりだ」と答えた日本の高校生は7.5%だった。 残り92.5%の高校生は、「自分には価値があるか」という問いを前に疑いなく「はい」と言わなかった。ちなみに同質問に対する他国の回答結果は、アメリカ57.2%、中国42.2%、韓国20.2%である。 結果を比較してみると、「自分には価値がない」という気持ちを抱えている日本の若者がいかに多いかが分かる。 勿論、日本の高校生達の回答には、謙虚さという概念に対して染み付いた意識や、自身を内省する率直さが含まれている可能性はあるだろう。 だが、それらを考慮した上でも自分自身を肯定する力が欠如していることは明らかだといわざるを得ない。この主張の裏づけとして、他の3つの質問事項と回答結果を挙げておきたい。 「自分を肯定的に評価するほうだ」6.2%(アメリカ41.2%、中国38.0%、韓国18.9%)。 「私は自分に満足している」3.9%(アメリカ41.6%、中国21.9%、韓国14.9%)。「自分が優秀だと思う」4.3%(アメリカ58.3%、中国25.7%、韓国10.3%)。 自己評価に関する質問事項への「全くそのとおりだ」という肯定的な回答は、どれも一割に達していない。 「国際比較・日本の子供と母親-国際児童年記念最終報告書」(昭和56年 総理府青少年対策本部)によると、当時の子供たちの自己評価もまた、国際的に見て著しく低いことが伺える。 このような結果から、慢性的に日本の高校生は自己に対する不足感、否定的な気持ちを抱えていることが分かる。 このような特徴は、十代特有の自然なものだという見方も出来るだろう。しかし、自分を認められない状況に生き辛さを感じている若者は多い。このような思いは、なぜ生まれるのか。 どのようにしたら、高校生の自己肯定感を育むことができるだろうか。
自己肯定感とは、教育的な文脈において「自分に対する評価を行う際に、自分のよさを肯定的に認める感情」(東京都教員研修センター)※2と表現されている。 自分という人間には良い部分だけでなく、直したい部分も勿論ある。それら両方を知った上で、自分自身のよさを肯定的に認める力のことを、自己肯定感と捉えられるだろう。 では、このアンケート結果が示す「自己肯定感の欠如」とは、何に起因しているのだろうか。おそらく、理由は単一的なものではない。 様々な理由が複雑に絡み合った結果だと想像するが、中でも私は「他者との関係性」が大きな要因ではないかと考える。 自己肯定感とは、外部が直接本人に与えられるものではなく、自身で見つけ、身に着けていくものだ。
だが、それは間違いなく他者との関係性に影響を受ける。周りから認められているという実感を持つには、自分を見守ってくれる、気にかけてくれる人の存在が必要である。 そこから、現代の子どもにとって、そのような役目を持った他者がいないという現状が見えてくるだろう。 これは、家族間の問題でもあり、友人関係の問題でもあり、教師と生徒の問題でもあり、もしくは親戚・祖父母といった血縁関係の問題でもあるだろう。家族や友人、教師との関係性は子どもの自己肯定感に大きな影響を与える。 なぜなら、子どもが過ごす環境としては、主に学校・家庭が挙げられるからだ。 しかし、そこで自己肯定感を得られるような関係性が構築されていない現状を踏まえると、それ以外の居場所を持つことも一つの解決策になっていくのではないかと考えられる。勿論、学校や家庭での他者との関係性を改善していくのも大切だ。
だが、学校には学校の、家庭には家庭の果たすべき役割がある。 教科教育を教える教師や、密度の濃い関係性を築く保護者という立場とは違った形で、子どもの身近に存在し、成長を見守ることが出来る存在とは、地域ではないだろうか。 私自身の経験を振り返った時、自分の子ども時代には家庭・学校という場の他に、地域が存在した。学校の先生や、両親以外にも、一歩外に出れば身近な場所には様々な生き方をし、考え方を持った大人がいる。 また、そのような人々が、自分のことを知っていて、見守っていてくれる。このようなつながりの実感は、常に意識してはいなくとも、自分を肯定する力の根っこであったように感じる。
高校生活を送る中では、なかなか地域の人々と関わる機会はないだろう。 だが、世代も暮らし方も様々な人々との関わりあいがあることで、自己や他者に対する捉え方・考え方は少しずつ変化していくのではないだろうか。 そのような関わりが、幼い頃から彼らの身近に存在していること、それが地域のコミュニティが存在する意義であり、現在の高校生における自己肯定感の欠如を改善する一つの解決策になっていくと私は考える。 教師や保護者とは違い、適度な距離をもって付き合うことの出来る地域は、学校・家庭とは異なった他者として子どもたちの自己肯定感を育む力に成り得るのではないだろうか。 勿論、社会にいる大人全員が高校生のお手本になるべき人格を持っているとは限らない。一般的な考えでは、接触を避けることが望ましいとされる大人もいるだろう。 しかし、反面教師のような役割も含めて、集合的に成り立つからこそ“地域”の多様性が際立つとも言えるだろう。 世代や価値観の異なる人々の集合体である地域のコミュニティは、子どもたちの自己肯定力を促す可能性を秘めていると考える。
本研究は、高校生に見られる「自己肯定感の欠如」を改善する一つの方法として、“つながり”を生む地域コミュニティの可能性を探るものである。 生活様式やコミュニケーションの形態が刻々と変容する現代において、他者や他者との関係性に対する人々の意識は大きく変化した。 本来身近にあった地域のコミュニティに対しても、それらの変化を受けて再考する必要があるだろう。 そこでまず、第一章では現代における地域という共同体を捉え直し、人々のつながりの現状を探る。 第二章では活性化するコミュニティ活動を分析しながら、つながりを回復するコミュニティの形を模索する。 これらの考察を交え、第三章では子どもと地域とつなぐコミュニティの在り方を提示し、理想の地域コミュニティとはどのようなものかを明らかにしたい。 この研究によって、地域コミュニティが子どもを育てる環境であることを認識し、子どもにとって地域の人々とのつながりが身近で自然なものとなること、自己肯定感を養える場となることを期待している。
第一章 地域コミュニティの現状を探る
第一節 コミュニティに関する人々の意識変化
子どもと地域の関わりを生むコミュニティを探る上で、地域コミュニティとは何かを捉えることは不可欠である。 普段の生活の中で私たちが“地域”や“地域のコミュニティ”というものを認識する機会は少ない。 それは現在、地域のコミュニティというものが崩壊の道を辿っていることを示している。 その理由は、人々のコミュニティに対する意識が、高度経済成長期を境に大きく変容したという点が上げられる。 文化・技術の発展に伴って私たちの生活様式が大きく変化したこと、それに比例して私たちの価値観や意識がどのように変化していったのだろうか。
元来、農耕民族であった日本人は集落と呼ばれるムラ型の社会を築いていた。 ムラとは、血縁関係にある家族を一つの単位として、複数の家族で成り立つ集合体である。生活の中心である農業はもちろん、冠婚葬祭などの儀式や行事、川・森林といった共有資源の管理まで、村の住民が協力して行っていた。 村の決まりを遵守し、共同体に対して献身的である限り、身分や生活は保障される。一方で村八分という言葉があるように、決まりを破れば村から追放され、生活の基盤を失ってしまう。 ムラ型社会では、村人同士の協力・協働なしに生きていくことは不可能であった。そのような環境だからこそ、村人たちは直接的な関わり合いを持っており、その為地域のコミュニティは自然と人々の生活の中に存在していたと考えられる。 ムラ型社会を構成する一員として、村人同士は互いを“一個人”として認め、関わりあって暮らしていた。 このような生活様式の中では、コミュニティという言葉は無くとも、人々は常に他者とのつながりを重要視し、その中で生きていたのである。
ところが、時代が進むにつれてこのムラ型社会の崩壊が訪れる。高度経済成長期以後、人々の生活は様々な場面で個別化していった。 一言で表すならば、生活の基盤であったムラ型社会という括りがなくとも、個人単位で暮らしていくことが可能になったのである。具体的な変化を見てみよう。 1960年代から70年代にかけての日本の経済発達は眼を見張るものだった。工業化が進んだ影響を受け、村の中で収まっていた生産・消費構造が、外部からの供給を受けられるようになった。 雇用やより近代的な暮らしを求めた人々は住み慣れた土地を離れ、発展した都市に移り住んだ。また交通手段の発達によって人々の生活圏が拡大したため、それまでと同じ土地に住みながらも、人々が地域に居続けることは少なくなった。 このような変化によって、地域社会から次第に人の姿が消え、同時に地域社会そのものの廃退に繋がっていったと考えられる。実際の生活における変化に加え、通信手段の発達は経済成長期以後のコミュニケーションの取り方を大きく変えた。 それは、人々の“他者との関係性”という意識を変えたことを意味する。ムラ型社会において、他者と関わるということは、実際に顔を合わせ、時間と場所を共有する中で行われた。 一方現代では、通信技術の発達やインターネットの普及によって、同じ場所に居ることなく、即時に相手とやり取りをすることが可能になったのである。
生活場所や生活様式、コミュニケーションの取り方まで、人々の暮らしからは様々な制限が取り外され、選択肢が増えていった。 このような生活の多様化は、人々の価値観の多様化に直結している。これは、自身の価値観に合わせ、自分と関わりのあるものを自分で選択・決定することが可能になったということだ。 ムラ型社会において自分とは切り離せなかった地域という存在は、現代自分とは関わりのないもの、自分が“属していないもの”として扱うことが可能になった。 自分と繋がりのあるもの、切り離せないものという意味において、自己に含めていた範囲が縮小していると言える。 物理的な生活の変化は、人々の意識の中からもまた地域への帰属意識を薄れさせていったのである。他者に対する意識についても同様の指摘が出来る。 生活の主体が村や家族から、個人へ移り変わっていくということは、自己と他者との切り離しが少なからず意識の中で起こっているということである。 実際に普段の生活の中では、他者を一個人として認識しなくとも、機械的なやり取りのみで暮らしていくことが可能になった。 このような他者に対する意識では、住民同士が関わりを持つ必要や機会はますます減少し、地域社会は廃退の道を歩むことになるだろう。
高度経済成長期を跨いで、人々の生活は随分と変化した。それに伴って、コミュニティや人との関わりに対する人々の意識も大きく変わってきている。 ムラ型の社会から、個人を主体とする社会への移り変わりの中で、地域住民の結びつきは薄弱化し、地域社会への人々の関心も薄れているのが現状である。 同じ地域に住みながらも、住人同士が同じ価値観を共有していない現代において、どのように地域のコミュニティを構築できるのだろうか。 また、地域のコミュニティは必要とされているのだろうか。コミュニティに対する人々の意識変化から、現代の人と人との関わりに焦点を移して考えていく。
第二節 現代の人と人との関わり
異なる価値観を持つ人々に、地域という一つのコミュニティを認識してもらうにはどうすれば良いのか。 そもそも、現代において地域コミュニティは必要なのだろうか。その答えは、現代の人と人との関わりの中にあると私は考える。
生活の個人化が進んだ現在、究極的な発想をすれば、個人は自己の生活の充足だけを求めて生きていけるということになる。 例えば、急に雨が降ってきて自分の家の洗濯物を取り込んでいる時、隣の家の洗濯物がまだ干されていることに気付く。 隣人はまだ雨が降ってきたことを知らないようである。そのような場合、何らかの方法で隣人にその旨を伝えるか否かは何によって判断されるだろうか 。恐らく、それは本人の善意や良心よりも、隣人との関係性にかかっていると考えられる。 勿論、隣人の洗濯物が雨に濡れてしまっても、自分が困るわけではない。 そのように考えて、そのまま自分の洗濯物を取り込むことも出来るだろう。 このように自己の生活の充足だけを追及して生きていくことは可能であるが、果たしてそれは本当の意味で充足していると言い切れるのだろうか。 例え隣人との関係性を持っていなかったとしても、濡れてしまう洗濯物を認識すると同時に、何かしらのアクションを起こすべきだろうか、という気持ちは生まれてくるのではないだろうか。
現代の人と人との関わりは、必然的な接点や何かしら共通した価値観を持たない限り、隣に住んでいる者同士であっても関係性を持とうとしない。 確かに人と関わるということは、プラスの面もマイナスの面もあることを認めなければならない。 他者との関わりは時に安心感や連帯感というように感じられる場合もあれば、しがらみや鬱陶しいもののように感じることもあるからだ。
しかしこれらは全て、当たり前ながら他者との関わりがあってこそ生まれるものである。 必要に迫られない限りつながりが生まれないという状態が続けば、コミュニティというものは共通項を持つ者同士の集まりとなり、細分化を続けていくことになるだろう。 自分と似た価値観を持つ人や、自分と同じものに所属している人とのコミュニティは生きていく上で必要である。 そこで学ぶことや得られるものは大きい。 しかし、それと同様に自分とは異なる価値観を持ち、自分とは違う暮らしをする“他者”と関わっていくことも、自身の価値観を拡げ、生きていくためには欠かせないことではないだろうか。
地域のコミュニティとは、人々にとって一番身近な他者の集合体であり、そのような人々と関わることが出来る場であると考えられる。 世代や価値観の異なる人々と関係性を持つことが疎遠にされがちであるからこそ、地域のコミュニティが現代の人々に与えられるものは貴重なのだといえるだろう。
地域のコミュニティの必要性に加えて、共通する価値観を持たない住民たちに地域というものを意識してもらうには、どうしたら良いのだろうか。 人々の価値観が多様化する中で地域のコミュニティを成立させるためには、住民たちが各々の考えを持ちながらも、ある部分で共通する価値観を持つことが不可欠だと考えられる。 人々の意識を地域に向けるためには、「その地域に住んでいる」という共通点に価値を持たせることが必要である。そうすることで、住民に同じ価値観を共有してもらうことが出来るのではないだろうか。 地域社会が発展することによって、自己の生活もまた豊かになる。このような考えは、個人の生活が地域というものの中で成立していることからも理解出来る。 先ほど例として挙げたような些細な助け合いの場面から、住民同士が顔見知りであることで犯罪抑制の効果があることなど、地域のコミュニティが機能することによって暮らしの質を向上させていく可能性があることは明白である。
現代の人と人との関わりの特徴は、同じ価値観を持つ者同士のコミュニティは構築されるが、地縁的なつながりは重要視されず、それゆえコミュニティは細分化の道を辿るということである。 地域のコミュニティを構築するには、きわめて難しい条件がそろっていると言わざるを得ない。 しかしながら、地域の住民同士のつながりが必要であるのは、子どもの自己肯定感を養うためだけではなく、地域住民全体にとっても個々の生活の本来の意味での充足という価値があることを忘れてはならないだろう。
第三節 地域コミュニティという定義
地域コミュニティというものを捉えるために、第一節では人々の意識、第二節では人と人との関わりに焦点を当てた。 そうして分かったことは、人々の意識から地域コミュニティというものが薄れているという現状、そして価値観を共有することが地域のコミュニティ形成に不可欠であるということである。 それらを踏まえ、地域コミュニティという言葉の定義を明確にしながら現代において目指すべき地域コミュニティの実態を捉えたいと思う。
地域コミュニティという言葉は、文脈によって微妙に異なる意味を持つことが多い。 一般的にコミュニティという言葉は共同体や地域社会と和訳されることが大半である。 共同体とは、血縁的、地縁的あるいは感情的なつながりを基盤とする人間の共同生活の様式、と説明される。 一方地域社会とは、自治の仕組みを含んで成立している生活共同体を示す(広辞苑)。共同体とはムラ型の社会構造におけるコミュニティを、地域社会とは現代の個人が主体となる社会構造におけるコミュニティを指しているのではないか。 共同体の持つ、つながりという概念と、地域社会の持つ機能的な意味合いの差は、それぞれの特徴を巧みに表現しているとは言えないだろうか。 さらに詳細な定義付けをしている例として、愛知県の地域政策課のデータを参考にしたい。
1969年から国の文書や文献、辞書などで使用された地域コミュニティという言葉がどのように定義されたかを調べ、それらの中から共通する内容を抜き出したものである。 「地域コミュニティに関する基本的事項」※3によると、地域コミュニティとは①一定の地域を基盤に構築されたものであること、②地域住民を構成要素とし、住民相互のつながり、絆によって構築されたものであること、 ③暮らしやすい地域社会を実現するために、そこにクラス住民による自立的、主体的な地域づくり活動や地域課題解決等の取組みが行われるものであること、と表記されている(愛知県地域政策課)。
これらの定義を見ると、①の地域を基盤にするという点は共同体にも地域社会にも共通すると言える。一方で、②に含まれる、住民相互のつながりや絆という表現は、 共同体として地域コミュニティが成立していた時代に存在していたものである。地域社会として機能的に働いている現在の地域コミュニティにおいては、 つながり・絆という言葉で表される住民同士の信頼関係は確立されているものではなく、獲得すべき対象といえるのではないだろうか。 更に注目すべき点は③の、暮らしやすい地域社会を実現する、という価値観が定義として言及されている部分である。 この場合、暮らしやすいという言葉の主語に当たるものは地域住民全体である。共同体という言葉通り、ムラ型社会では地域が一つの生活体であり、生活の基盤として地域コミュニティが成立していた。 だが、現在では地域住民全体の暮らしやすさという価値観の共有を明確にすることで、地域を一つの生活体として表現し、地域コミュニティを構築していこうとする動きが見られる。
以上の記述から、地域コミュニティという言葉の定義付けは、現在の実態だけではなく、目指すべき形を含めた上でなされていることが判明した。 そこで、本研究においては目指すべき地域コミュニティの形を、共通した価値観で結ばれた一定地域の住民による、信頼関係で成立した活動体であると定義付ける。
第二章 活性化するコミュニティ活動の現状
第一節 テーマコミュニティ活動とは
第一章では、現代において目指されるべき地域コミュニティの定義付けを行った。 地域コミュニティとは、共通する価値観を持っていること、一定地域の住民によるものであること、住民同士に信頼関係が成立していること、の三点を満たす活動体である。 中でも、三点目に着目したい。現代において、地縁的なつながりを持った人と人との関わりは減少している傾向にある。 そのような状況下で、住民が信頼しあう関係性の構築を行うことは容易ではないだろう。しかしながら、人々の意識が地域というコミュニティから離れている現状に対して、危惧を抱いている人々がいることも忘れてはならない。 行政、市民団体、NPO団体、そして個人という様に、各々の立場の人々が独自のコミュニティ活動を行っているのが現状である。
コミュニティ活動とは、地域コミュニティ活動とテーマコミュニティ活動の二つに分類される。一般的にコミュニティ活動という言葉が使用される場合も、この二つのうちのどちらかを指していることがほとんどである。 地域コミュニティ活動とは、主に行政や自治体によって行われる、地域を基盤とした活動である。 自治運営や、住民同士の交流を目的とした地域のイベントの開催、そして地域特有の課題を解決するための取組みなどが活動内容に含まれている。
一方で、近年活性化しているテーマコミュニティ活動とは、地域を限定せず、特定の課題を解決・改善することを目的としたコミュニティ活動である。 特徴としては、第一に課題を一つに絞っていることから活動内容が理解しやすく、それゆえターゲットが明確であるという点が挙げられる。 課題に共感したり、実際にその課題を自分が抱えていたりする場合、初めてでも活動に参加しやすいと言えるだろう。 また、同じ課題を共有している人同士で成立するコミュニティであることから、参加者同士の関係性も生まれやすい。
第二の特徴は、コミュニティ活動をする団体の専門性が高く、参加者のニーズに合わせて細やかな対応をする事が可能であるという点である。 課題を持つ人々にとって、その課題を専門として扱っている活動者と直接やり取りできる場は貴重なものであり、相談できる他者がいることは大きな安心感を生むだろう。
テーマコミュニティ活動の事例として、NPO法人カタリバによる高校生のキャリア支援活動が挙げられる。 NPO法人カタリバは、「将来を考えるきっかけを、親でも先生でもなく、友達とも違う関係で与えたい」という理念の下設立された。 主な活動内容は、大学生のボランティアスタッフらが高校に出向き、高校生と進路や将来について語り合う、カタリ場と呼ばれるイベント型キャリア支援である。 また、2011年からは東北復興支援事業として被災地での学習支援にも取り組んでいる。
カタリ場は、学校側が授業の一環として団体と協力し成立している。 これは、生徒たちにとって教師や保護者ではない立場の他者との語り合い、関係性を築くことが、進路や将来を考える上で重要であるという学校側の認識を示している。 また高校生にとっても、現役の大学生と話をすることを目的に向き合う機会は貴重なものであるといえる。 実際にカタリ場の風景を収めた映像からは、自分の悩みや将来への不安、大学生活への期待など、様々なことを話したい、聞きたいという欲求を持っている高校生の姿が見受けられる。 地域を特定することのないテーマコミュニティ活動として、NPO法人カタリバのキャリア支援は青森や沖縄など地方のモデルケースになっている。
テーマコミュニティ活動が現代の人々に受け入れられるのは、共通した価値観で活動側と参加者側が結び付けられているからである。 カタリ場の例で言うと、進路や将来について考える機会を提供したいというカタリバ側の思いと、生徒たちが持つ進路・将来に対する漠然とした不安と向き合いたいという気持ちとが合致し、このような場が成立していると考えられる。 テーマコミュニティ活動によって、人と人との関係性が構築されることは明確である。更に、モデルケースとして他の地域でも活動に取組みやすいというメリットがあり、近年活性化していることにも頷ける。
だが一方で、この活動によって生まれた関係性が、子どもたちの身近に存在し、彼らの成長を見守る役割を果たすことはない。 活動として生まれた人と人とのつながりが、日常生活の中で起こるようにするためには、 コミュニティ活動を地域のつながりを生むものへと発展させる必要があるだろう。 そこで、地域に根を張ったコミュニティ活動としてソーシャルビジネス、コミュニティビジネスという活動に焦点を当てる。
第二節 ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスの台頭
ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスとは、課題解決の手法としてビジネスの視点を取り入れたコミュニティ活動とのことを意味する。 ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス共に、様々な社会的課題を市場として捉えており、高齢化問題や環境問題、子育てや教育に関する問題など、取り扱う問題は多岐に渡る。 二つの言葉の違いとしては、ソーシャルビジネスには活動領域や解決すべき社会的課題に一定の地理的範囲が存在しないが、コミュニティビジネスには地理的範囲が存在するという点である。 経済産業省によると、コミュニティビジネスは地域資源を活かし、創業や雇用の創出だけでなく、働きがいや生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与すると考えている。 地域活性化と経済の発展のという双方の課題を解決する新しいビジネスの手法として、注目が集まっている活動体である。
ビジネスの視点をコミュニティ活動に取り入れることが、どのように地域のコミュニティ作りへとつながっていくのだろうか。それはソーシャルビジネス、コミュニティビジネスの特徴を見ていけば分かりやすいだろう。
第一に挙げられるのは、純粋に利益のみを追求するビジネスとは違い、社会性を持った理念と事業性とを兼ね備えた活動であることだ。 社会における課題解決を目的としているため、企業側の理念に共感する顧客が生まれる。 それは、課題解決をしたい、そのための力になりたいという一つの価値観を共有した関係性だと言える。 コミュニティビジネスに絞って言及すれば、地域の課題に対してアプローチする企業が存在することで、地域の人々にとっても問題が可視化されることになる。 更に、その問題に対して地域の住民から共感を得られるということは、地域という集合体として一つの価値観を共有していく土台となるだろう。
第二に、地域でビジネスを行うことによって、新たに地域に雇用を生み、地域を基盤とする経済の仕組みが生まれるという点である。 地域で雇用や経済活動の仕組みが生まれることは、顔が見える直接的なつながり作りに結びついていると言える。 また、先ほどの価値観の共有という点と合わせると、単なる企業側と顧客との関係性に留まらず、直接的なやり取りを通して地域の住民を個人として認識する関係性を生むことが可能である。 サービスとお金とを交換するというシステムの上に成立しているからこそ、このようなコミュニティ活動が現代の人々に受け入れられるのではないだろうか。
経済産業省から刊行されたソーシャルビジネスケースブック(地域経済産業グループ、2011年)※4では、全国で実際に行われたソーシャルビジネス、コミュニティビジネスの事例を紹介し、今後活動を行っていく人々に向けて支援を行っている。 様々なプロジェクトが挙げられているが、中でも三重県で行われた、地域活性化並びに子どもを育てるという視点を持った活動事例に注目する。
三重県の多気町は、地元の高校生を中心としたコミュニティビジネスが行われている。町内には、三重県立相可高校食物調理科の生徒によって運営されるレストランがある。これは、農業の活性化と若い世代の活躍の場の提供を目指して、当時の多気町の農林商工課主幹者が高校教諭に協力を依頼したことで実現された活動であった。高校生が経営する飲食店は話題になり、地域内・外の人々が訪れるようになった。その後、この科の卒業生の中から就職のため地元を離れるものの、厳しい料理修行の中で地元の戻る生徒が多く見受けられるようになる。そこで、若者の雇用を目的とした卒業生によるソーシャルビジネスとして、惣菜・お弁当屋を立ち上げる。これらは地元のスーパーに卸し、地域の人々のもとへ届く。そして現在、同校の生産経済科の高校生を中心に、企業、農業生産者、JA、町役場、NPO、大学、ボランティアなどが連携し、農産物特産品を活用したハンドジェルの製品開発および販売を実施するに至った。多気町の事例は、農業の活性化と若者の活躍の場を与えることを目的として始まったが、現在では立場の違う様々な団体が協働し、高校生を中心としたコミュニティビジネスを成功させている。
この活動において面白い点は、第一に若者を地域の中心に置いてしまうことである。地域コミュニティを形成する上で、若い世代を組み込むことは容易ではない。若者を対象とするのではなく、活動の主体にすることで地域住民からの関心が高まり、結果的に住民が自らの地域を強く意識することに結びついたと言える。第二に、コミュニティ活動の輪が広がっていくことである。高校生によるレストラン運営から、卒業生の働く場、そして別学科の生徒の商品開発というようにプロジェクトが進んでいく。それに比例して地域内・外での認知度が高まり、協力する団体も増えてくる。また地域住民もビジネスとして提供されるサービスや商品を購入することで、活動を応援しながら自らも地域活性化の一員として活動に参加するという構図が出来上がる。このようにして課題を解決しながら、地域としてのまとまりを見せていく多気町のコミュニティビジネスは、地域コミュニティを形成する上で理想的なモデルケースであると言えるだろう。
第三節 つながりを生むコミュニティの形
テーマコミュニティ活動、またソーシャルビジネス、コミュニティビジネスの活動を見てきた結果、様々なコミュニティ活動が人と人との関係性を構築していることが分かった。これらの活動から、確かに団体と参加者とのつながりは作られていると言えるだろう。だが、地域住民同士のつながりという視点から見ると、信頼関係によって成立したコミュニティを形成するにはもう一歩踏み込んだ活動が必要だと考える。課題解決という目的や事業性を持ちながらも、コミュニティ活動がより地域住民の関係性作りの基盤として機能することはできないだろうか。様々な団体によるコミュニティ活動が行われている中で、自らの活動だけでなく、地域のコミュニティ作りを意識した活動を見ながら、つながりを生むコミュニティの形を模索したい。
株式会社ソーシャルエナジーカフェは、障がい者支援を軸としたソーシャルビジネスを行う会社である。 しかし、代表の木村知昭氏お話や、日頃のカフェの様子から、社会的な活動と同等に、人と人とがつながる場としての機能を持っているという印象を受ける。 美味しい社会貢献というキャッチフレーズの通り、ソーシャルエナジーカフェは全国の障がい者福祉施設で作られた食品から、スタッフが本当に美味しいと感じたものを厳選しカフェのメニューとしてお客に提供している。 カフェといっても店内には縦長のテーブルが一列に並べられており、ここへ集まった人は皆食事の席を共にする作りになっている。 2009年に設立されて以来、新聞や雑誌といったメディアへの掲載や大学での講演活動など、新しい社会貢献の形として注目を集めている。
しかし、私が着目したいのはソーシャルエナジーカフェの地域コミュニティ形成基盤としての側面である。木村氏がこの事業を始めたのは、企業の中で大きな影響力を持つよりも、数人とでも顔の見えるつながりを持ちたいという思いからであった。カフェは日中フリースペースとなっており、近隣の学生や個人営業主が作業をしながら会話する様子が見られる。夕方からは、様々なテーマで活動する団体にスペースを貸し出すことや、ソーシャルエナジーカフェが主催となってイベント行う場合が多い。他団体の活動を支援することで、人の輪が広がり、顔の見える直接的なつながりが日々生まれている。
また様々な主旨を持った団体がイベントを行うため、ブログやツイッターといったメディアを通して情報を知りえた人が遠方からカフェを訪れることもある。常連の客、初めて店を訪れる客、イベントを開催した団体、そしてお店のスタッフまで様々な立場の人が入り混じり、一つの空間と時間を共有している。コミュニティを構成するメンバーは流動的であるが、訪れれば必ず誰かに会うことが出来る開かれた場所として、ソーシャルエナジーカフェを拠点としたつながりが地域に存在している。
もう一つ、地域のつながり作りを意識した事例として、世田谷区上北沢にある一軒家、岡さんのいえTOMOという地域コミュニティ活動を紹介する。昭和から残る木造の住宅は、岡ちとせさんという故人の所有物であった。岡さんがお亡くなりになられる際に親類が譲り受け、子どもや地域の方のためにこの家を役立てて欲しいという故人の願いを実現するために地域共生のいえとしてオープンさせた。
地域共生のいえとは、財団法人世田谷トラストまちづくりによる支援事業の一環であり、個人の住宅を地域に役立てるために開放するという取組みである。2007年からスタートしたこの活動は、オーナーの小池良実氏やボランティアスタッフによって運営されている。カフェスペースになったり、駄菓子屋になったり、子どもの遊び場になったり、大人の集会所になったりと、地域に開かれた家は曜日ごとに違った顔を持ち、様々な世代の人同士の交流が生まれている。
近隣のお年寄りが岡さんのいえTOMOの玄関口で開く駄菓子屋は、近くにある小学校に通う生徒で賑わう。週に一回のペースで開催されるため、定期的に子どもたちが地域コミュニティ形成の場に足を運び、地域の人々と関わる仕組みが出来ている。子どもが無意識のうちにそのような場所に触れる機会を得ることで、地域コミュニティが自然と彼らの身近に存在することは、つながりを生むコミュニティとして理想的であると言えるだろう。
また、庭の木々の手入れや岡さん直筆のレシピ本の再現、ホームページの更新や刊行物の制作など、場所を維持するために必要な活動は、それぞれを得意とする地域の人々の協力を得ながら活動を続けている。世代も生活環境も異なりながら、一つの空間の中でそれぞれが役割を持ち、それを互いが認め合っている関係性が生まれている。一つの場所に対して自分が関わっていること、他者と共有していることを、地域の人々が実感していることが分かる。
これら二つの活動事例から、つながりを生む地域コミュニティの基盤として、三つの要素が重要であると考える。 第一に、コミュニティ活動体が場を持つことである。地域に根差す場を持つことで、地域の人々の居場所・交流の場を常に地域の中に維持出来る。また、場所とそこで過ごす時間や経験の共有は、人々に地域でのつながりを意識させ、自分もまたコミュニティの一員であることの自覚を持たせるだろう。第二に、出来事が起こるということが重要であると考える。常に同じ場所に存在しながらも、様々な経験が出来る場所であることによって、人の流れが継続的に起きることになる。新しい出会いやつながりのきっかけを生み出していく仕組みとして、コミュニティの活性化に繋がるのではないだろうか。第三に、世代、性別、職業が異なる人々が、コミュニティの中において自分の役割を持つことである。そのコミュニティ活動を維持したい、大切にしたいと思う気持ちは、自分自身がそのコミュニティに属しているという実感が生むものである。これにはコミュニティ活動に参加する動機付けという意味合いが強く含まれるが、作業としての役割でなくとも、自分がその場所に関わることに対して肯定的な気持ちを持つこと、それを互いが認め合える状態こそ理想的なコミュニティと言えるだろう。
第三章 子どもを育てる地域のかたち
第一節 高校生を取り巻く他者との関係性
第二章では、3つの種類のコミュニティ活動について、それぞれの事例を交えながら検討した。その結果、つながりを生む地域コミュニティに必要な要素とは、場を所有すること、経験を提供出来ること、そしてコミュニティに対する帰属意識を高めるための動機付けが出来ることであると考える。地域のコミュニティが子どもの成長を見守り、家庭や学校とは異なる地域独特の子育てにおける役割を果たすためには、地域コミュニティと子どもという存在をどのように結びつけるかが重要となってくる。そこで第三章では、地域がどのようにして子どもにアプローチすべきか、またアプローチすることが可能かという視点から子どもを育てる地域の形を考える。
まずは現代の子どもにとっての他者との関係性を捉えることで、今身近にいる他者と、地域コミュニティとが果たすことの出来る役割の違いを明確にしたい。冒頭で引用した「高校生の心と体に関するアンケート」によると、親が自分の優秀さを評価しているかという質問に対して「はい」と答えた生徒が約3割であった。同様に教師が自分の優秀さを評価しているかという質問については2割の生徒がそう感じているという回答をしている。高校生が関わる大人として、一番身近にいる保護者や教師から、彼らは認められている実感を得ていない現状が見受けられる。親が勉強についてのアドバイスをすることや、生き方を教えることについても相対的に不快な感情を抱く生徒が多い。また、教師に対して相談がしやすいかという項目に対しても、しやすいと答えた生徒は全体の3割に満たない。
これらの高校生の特徴は、年齢に伴う発達段階の一部として自然なものであるという見方もできる。杉本希映、庄司一子「「居場所」の心理的機能の構造とその発達的変化」(2006)によると、子どもは自らの発達段階に応じて、居場所から心理的に得ようとするものが変化するという。主に小学生の頃に家庭という居場所から与えられていた安心感を、中学・高校生になると友達との居場所から得ているという調査報告がある。
それでは、友人との関係性について聞いた質問事項を見ると、友人と一緒にいる時間は気が楽である、楽しい、という肯定的な意見が多い。だが一方で、相談できる友達がいるかという質問に対して「はい」と答えた生徒は少ないという結果が出ている。更に悩みがある時、ストレスを感じた時に取る対処法として、寝る、一人で遊ぶ、我慢する、といった他者に頼らない傾向が見られる。悩みやストレスに対して自立した態度で向き合う能力は必要ではある。
しかし、睡眠をとることや我慢をすることは、自立した態度というポジティブなものというよりも、一時的な解決に過ぎないのではないだろうかという見方も出来る。杉本・庄司(2006)は「「居場所」を他者とのかかわりの中で持てるようになることも大切なことであるが、それとともに「自分ひとりの居場所」で得られる心理的機能から、精神的なバランスを回復することも、ストレスフルな学校や社会に生きる現代の子どもたちにとって重要なことといえるのではないだろうか。」と述べている。現代の高校生にとって、一人でいる時間や空間は生活の中で重要視されており、その重要性を周囲も認める必要がある。
しかしその後、中島・倉田(2004)の研究を持ち出し、「1つの「居場所」のみで、「居場所」から得られる心理的機能をすべて充足することは困難であること」を確認している。そこから、他者との関係を構築する意義も十分に存在していることが分かる。一人でいることを高校生たち本人が重視しているからこそ、それ以外の居場所、他者とのつながりを生む場所について、外部からのアプローチが必要であると考える。
第二節 子どもに対する地域という他者
高校生にとって、生活を共にし、互いを知っている他者との関係性というものは、自分一人で過ごす時間や場所とバランスを取った形で構築されていることが判明した。特に、親と子、教師と生徒という異年齢、立場の異なるつながりについて、年齢的な発達段階の影響もあり、子どもたち自身は肯定的な感情を抱いていない。それでは、そのような他者との関係性を持つ高校生にとって、地域というコミュニティが果たすことの出来る役割とはなんであろうか。それは、今彼らの身近にいる他者と何が違うのだろうか。
地域の人々と子どもたちとの関係性は、今彼らの身近にいる家族や友人、教師といった他者との関係性には無い特有の距離感がある。一人の居場所・時間を持つことでストレスフルな人間関係とのバランスを取っている高校生にとって、この適度な距離感のある関係性は今までに無かったつながりだと言える。一人か、他者かの二択であったところに、地域の人々という新たな他者は第三項として新しい自分と他者との関わりの可能性を生むだろう。
適度な距離感といっても、物理的なものから精神的なものまで様々な表現が出来る。まず、物理的な距離感としては、高校生活を送る上で、地域の人々と子供達とが互いに出会う機会は少ない。しかし、同じ地域に暮らしているため、顔を合わせられる範囲に常に互いが生活していることを知っている。常に共に生活するのではないが、同じ生活圏を持って暮らしているという距離感は、挨拶を交わしたり、姿を見かけたりという何気無いやり取りを生むだろう。精神的な距離感としては、関係性の深さという面から地域と高校生との関係性を考えたい。触れ合う機会が多くは無いため、全てを話せるような親密な間柄になるには、時間やきっかけなどがない限り難しいと予想される。だが教師や親とは違い、地域の人々と高校生は直接的な利害関係にない。その分、本音をこぼせる余白があるのではないかと私は考える。常に向き合って関わっていく関係性は、互いを思いやったり、意見の衝突が起こったり、深く付き合う分関係性の密度も濃くなる。そのような関係性が大切である分だけ、重く負担になることもある。しかし、互いをよく認識していないとしても、適度な距離感を持った関係性だからこそ、一時的に核心に触れた会話が出来る可能性を含んでいる。また保護者や教師、友人の様に、毎日顔を合わせ、自分のことを良く分かっている相手ではないという点は、場所に合わせて保ってきた自分とは異なる自分の側面を他者の前に出すきっかけにもなるだろう。
学校では学校の、家庭では家庭での自分らしさや、周りから認識されている自分というものにとらわれず、他者と接することができれば、違った側面の自分でも素直に受け止められるようになるだろう。
地域の人々と高校生の間に存在する適当な距離感は、他者との関係性でストレスを感じ、一人の時間を重視する高校生にとって、クッション材のような役目を果たすのではないだろうか。高校生が、第三者的な立場で話を聞いてくれる他者を求めていることは、カタリ場の例からも明らかである。
実際に私が高校生であった頃、学校の近所に「ひつじ喫茶」という看板の立った小屋が出来た。ここは30代の男性が、会社を辞めて始めたカフェであった。店内にはその人がセレクトした本が無数に置いてあり、そこでは本を読むことも、一緒にカフェに訪れた人と話すことも、店のオーナーと話すことも、勉強をすることも許されていた。時間と空間を共有していて、挨拶など直接的なやり取りはするが、必然的に他者と関わる必要性がない。そのような空間の居心地のよさは、高校生だった自分にとって新鮮であったことを覚えている。特に大学受験前の時期であったからか、進路選択に迫られて漠然と不安に思っていたことを、ほぼ面識の無いオーナーに話してしまった事がある。タイプの異なる友人たちもまた、自分の将来のことや、最近考えていることなどを素直に話すことが出来ているように感じた。
この事は、継続的に濃密なコミュニケーションを取ることのない関係性が、緊張を和らげた結果だと考えられる。必然的に関わる必要性が無い関係性を持てることは、高校生にとって新しい他者との関わりである。そして、そのような関係性こそ、地域の人々によって生み出すことのできる、特有のつながりではないだろうか。このようなつながりを地域と子どもとの間で生むことが出来れば、高校生にとって地域が果たせる役割は大きいと私は思う。
そのような関係性を持つことが出来る場を地域の中に置くこと、そのような地域コミュニティ活動を提供することが、子どもにとって一番の地域からのアプローチ方法であるだろう。また、そのような他者との関係性を持つことで、今現在高校生の身近に存在する他者との関わりそのものについての捉え方も変化していくのではないかと考える。
第三節 地域コミュニティ活動による高校生へのアプローチ
地域が子どもに対して与えられる他者としての関係性は、適度な距離感を持っているという点において他の関係性とは異なっている。高校生が地域の人々とそのような関係性を築くためには、どのような地域コミュニティ活動が理想的なのだろうか。高校生に対して、地域コミュニティが果たすことの出来る役割の希少性や必要性について述べてきたが、高校生自身が地域コミュニティの価値を認められるようなアプローチの仕方が必要であると言えるだろう。
現在の状況下において、残念ながら高校生が地域コミュニティの価値を認識しているとは言えない。よって、そもそも高校生は地域のコミュニケーションを必要としているかという疑念に対しても、現時点ではほとんど必要としていないのではないかというのが私の意見である。
その理由は、彼らにとって地域コミュニティが異物な存在であるからだ。幼い頃から自然と接していないものに対して、帰属意識を持つことは難しい。ましてや地域コミュニティの再生や再構築が叫ばれる時代において、実体のない地域コミュニティを認識することは困難を極めるだろう。そのような状況で、地域コミュニティを必要とする高校生がいるとは考えにくい。
では、どのようにしてそのような世代の子どもたちに地域コミュニティの価値を認めてもらえるだろうか。即時的にこの問題を解決することは出来ないだろう。地域の人々のつながりは、長い年数をかけて生活や意識の変化と共に徐々に失われてきた。私たちは今後、それと同じ年数をかけて、現代の生活様式や人々の意識に合ったコミュニティの形を模索しながら、少しずつ再構築していかなければならない。
世田谷区にある地域共生の家「岡さんの家」を運営するオーナーから、このような話を伺った。実際に、幼い頃から親と共にコミュニティ活動の場に関わっていた子どもが、小学生になっても気軽にそのコミュニティに立ち寄るというものである。
それはおそらく、保護者と共に幼い頃から慣れ親しんだという安心感や、少し年上の子どもたちが遊ぶ風景を見てきた経験などが、その子に蓄積されてきた結果ではないだろうか。その子どもが中学、高校、大学へと進学し社会人になってもそれまで通りコミュニティに携わるとは思わない。だが、幼い頃に家族や教師とは違った文脈の中で、異なる世年代の人々と出会い関わった経験は、必ず本人の中に残るだろう。
その経験があれば、彼・彼女が親世代になった時、あるいは地域の一員となって子どもに接する時、地域コミュニティに対する意識は確実に変化しているのではないだろうか。そうして起こっていく地域コミュニティに対する人々の意識変化は、次の世代の子どもたちと地域とを繋ぐきっかけに成り得ると私は考える。そのようにして段々と、コミュニティ活動に限らず、地域でのコミュニケーションを地域住民にとって身近なものにしていくことが出来るのではないだろうか。
地域コミュニティの存在を将来的に当たり前にすることで、地域という存在が自然と子どもの側にいる時代を作る。それが実現する時には、高校生はコミュニティを必要としているのか、という問いに新たな答えが出せると思う。
しかし、地域コミュニティに触れ合う機会がないまま現在高校生になった子どもたちに対しては、地域コミュニティ活動を通してそれ自体の価値を認めてもらえるようアプローチする必要性がある。
そのためには第一段階として、子どもたちが地域のコミュニティに意識を向けたり、自己と他者との関係性について改めて考えてみたりという機会を外部が与えなければならないだろう。そこで、現在の子どもの生活環境である学校と地域コミュニティ活動体との協力が不可欠となってくる。現在も学校とPTA、地域の住民などの連携により、通学時の見回りや挨拶運動、課外学習、校外学習などが行われている。教育実習生として教育現場に携わっていた期間中にも、中学校では地域の方を学校に招き講話を聞く機会や、体験学習のボランティアとして保護者や地域の人々と子どもたちとが触れ合う授業が行われていた。
このように、地域と子どもたちとの関係性を築くことが出来る場としての学校を窓口にすることは、子どもたちだけでなく保護者や学校側にも地域コミュニティ活動を認知してもらう機会となり、活動体に対する信頼度も高まるだろう。
実際には、地域コミュニティ活動体の活動内容を生徒たちに伝えること、体験してもらうことで興味を抱かせることが重要である。NPO法人カタリバの例を見ても、現代の高校生が第三者的な立場で話を聞いてくれる場を求めていることから、対話を通してコミュニケーションを取ることで、今まで自分の身近には居なかった世代・立場の人間との関係性を体感してもらうことが出来るだろう。生徒たちがその後、自主的にコミュニティ活動に参加したいと思い、行動に移すことができるよう、コミュニティ活動では定期的に学校を訪問したり、生徒たちとの対話の中で彼らの思いを汲み取ったイベントを共に行ったりと、少しずつ生徒にとって身近な存在へと近づいていく姿勢が必要になるだろう。このようなアプローチを取ることで、地域コミュニティを意識していない現在の高校生にも活動の価値を伝え、子どもと地域とを繋いでいく関係性作りを行うことが出来るだろう。
結論 地域コミュニティの実現を目指して
本研究は、高校生に自己肯定感がないという調査報告に対し、どのような解決策があるかという点からスタートした。その際、自己肯定感には他者との関係性が大きな影響を及ぼすことから、高校生にとって一番身近でない他者として、地域の人々、地域のコミュニティに可能性を見出せるのではないかと考えた。子どもが育つ環境として挙げられる家族、学校は、当然ながらその地域に成立するものである。しかしながら、現代の生活において地域との関わり、地域に住む人々とのコミュニケーションを取る機会は少ない。
それは、第1章で述べた通り、生活様式が変化したことによる影響が大きいだろう。また、それに伴う人々の意識変化によって、現在地域コミュニティはほとんど存在しないに等しい状況である。 しかしながら、本来地域というものは、人が育つ基盤にあるべきものだ。必然的な関わりがなくとも、同じ地域で生活する人々を認識しない人間はいないだろう。地域のコミュニティは、個々の生活を支え、自分たちとは切っても切り離せない存在だということを住民同士が認識し行動することで、個人の生活もまた豊かになっていくはずである。
そこで、本研究では地域の住民同士につながりを生み、地域コミュニティを機能させるためのコミュニティ活動に着目した。様々な活動方法や内容がある中でも特に、つながりを生むという機能にこだわったコミュニティの形の追及である。共通の価値観を持ち、信頼関係で結ばれた一定地域の活動体という目指すべきコミュニティづくりには、人々が時間や空間を共有できる場を所有し、人の流れを作るよう様々な経験を提供し、世代の異なる人々がそれぞれの役割やコミュニティに関わる動機を持ち、互いに認識している地域コミュニティ活動が必要である。
そのような地域コミュニティ活動に、本研究の論点である高校生を組み込んでいくためには、高校生にとって地域という存在の必要性を明らかにする必要があった。彼らにとって地域の人々とは、適当な距離感を持った第三者的な存在である。それは、一人で過ごすことで既存の他者との関係性で受けたストレスとのバランスを取っていると指摘される高校生にとって、新しい人と人とのつながり方である。現代人が失いかけている地域のコミュニティを、子どもの育つ環境の中に自然に根付かせることは、高校生の抱える問題だけでなく、地域の人々が抱える問題にもアプローチをしていく契機になるだろう。
地域コミュニティを根付かせる為には、コミュニティ活動を行いながら長い年月をかけて人々の関係性を構築してかなければならない。その実現に向けて今出来ることとは、コミュニティ活動の継続と住民の自主参加を促す仕組みづくりである。その流れを作る為に、今私たちに出来ることは何か。それは第一に、現在活動しているコミュニティ活動が出来る限り継続し、地域に根付くよう支援・活動することである。第二に少しずつでも、沢山の人にコミュニティ活動に触れてもらう機会を提供すること、また住民による自主的な参加を促す仕組みを持ったコミュニティ活動を行うことである。この二点を推進しながら、現在の生活様式に合ったコミュニティの形を模索していくべき段階が、今ではないだろうか。
コミュニティ活動は、草の根的に数を増やしてきているが、その活動はテーマを絞ったものが多い。理想のコミュニティの形として地域に存在するためには、常にその地に根をはるように場を所有することが必要である。細分化していくテーマコミュニティに対して、地域コミュニティは継続の壁と常に戦っているといえる。テーマコミュニティ活動が活性化している現状の流れが継続すれば、今後益々個別のニーズに応じた取組みが生まれてくることが予想される。
同時に、コミュニティ活動の主体も自治体、行政、NPO、起業家、ボランティアという垣根を越えた協働体制に向かっている。無論、地域によって活動内容や取組みの度合いは異なるが、コミュニティ活動は確実に活性化していると言える。母体数が増える分、時間の経過と共に「継続できるコミュニティ活動」と「継続できないコミュニティ活動」が出現するだろう。地域に根差したコミュニティを形成するためには、継続的な活動を行うことは欠かせない。
しかし、「継続できないコミュニティ活動」という存在があることもまた必要なことであり、自然なことだと私は考える。コミュニティ活動を行いたいという理念を実行に移したことで、地域の課題を可視化することができ、住民に地域というものを意識するきっかけを与えられるからである。現在はコミュニティ活動事例を集め、それらを参考により継続可能な活動モデルを模索している段階である。様々なチャレンジをする意義、それを記録として残し、今後のコミュニティ活動の継続発展に結び付けていくことが、地域コミュニティを形成していく土台となるだろう。また、より多くの人々にコミュニティ活動に触れてもらう機会を提供すること、住民による自主的な参加を促す仕組みを持ったコミュニティ活動を行うことの必要性を挙げた。
先に述べた通りコミュニティ活動自体は活性化している現状を踏まえると、様々なコミュニティ活動と地域住民が出会う可能性は決して低くは無いと言えるだろう。必然的でない関係性を作るということは、参加者にコミュニティ活動へ参加するか否かの決定権が委ねられているということである。勿論活動側が参加者をどう取り入れていくかという工夫は必要だが、参加者側も地域住民としての意識を持ち、自らの生活の基盤である地域に向き合うべきではないだろうか。
現在の地域や人々の生活は、よく整理・整備され、危険視されるものは排除され、極めて安全である。暮らしやすさを求め、大勢の人が努力した結果得られている生活であることに間違いはない。しかし、安全なものに囲まれ、守られて育った子どもたちは今、自己肯定感が持てないだけでなく、極めて複雑な家庭環境・学校社会の中で様々な問題を抱えている。思春期ということもあり、デリケートな心理状況を持つ彼らに対して、決め細やかなアプローチの方法は確かに必要である。しかし、社会で自立して生きていくためには、雑多な世界の中でも自分のやり方や考え方、価値観を維持できるようになる必要があることもまた、事実である。地域社会という他者が高校生にとって未知であるからこそ、その中で色々なタイプの人と知り合い、大人の生きる姿を間近で見ることで、家庭でも学校でも学ぶことの出来ない体験を培って欲しい。自分と異なる価値観を持った相手と出会った時、その人と自分との価値観の差異を認めることは、決して容易ではない。特に同世代の間では、自尊心が大きすぎると、相手のよさを素直に認められず、反対に自分を認められないままでは、相手に劣等感を覚えてしまう。世代や立場の異なる人々との対話、つながりの中で、他者を受け入れることを別の角度から学び、身に付けることで、自己肯定感を養っていく基盤となる力を付けていくことに繋がると思う。
今回の論文では、地域コミュニティの持つ可能性や、現代における必要性を述べたに留まり、理想のコミュニティ活動の形として既存の活動を参考により現代の人々の意識・生活にあった地域コミュニティモデルを作ることは出来なかった。今行われている活動を組み合わせるだけでなく、今後のコミュニティ活動が今を生きている人に広く受け入れられる地域コミュニティの形、地域のかたちを更に探っていくことが必要であると感じている。今まで同様、自分の生活の中にある地域との関わり、地域コミュニティ活動への参加を通して、自分もまた地域のコミュニティ形成の一員となっていきたい。
参考URL
※1財団法人日本青少年研究所 『高校生の心と体に関する調査』 2011
※2東京都教員研修センター 『子どもの自尊心や自己肯定感情について』
※3愛知県地方政策課 『地域コミュニティに関する基本的事項』
※4経済産業省 地域経済産業グループ 立地環境整備課 2011 『ソーシャルビジネス・ケースブック』
※5杉本希映・庄司一子『「居場所」の心理的機能の構造とその発達的変化』2006 日本教育心理学会 教育心理学研究 54(3), 289-299,
特定非営利法人 放課後NPOアフタースクール (2013/01/18)
経済産業省 ソーシャルビジネス/コミュニティビジネストップページ (2013/01/18)
株式会社ソーシャルエナジーカフェ(フィールドワーク、代表者インタビュー)
地域共生のいえ 岡さんのいえTOMO(フィールドワーク、代表者インタビュー)
参考文献
佐藤友美子 『つながりのコミュニティ』 岩波書店 2011
ジョン・T・カシオポ&ウィリアム・パトリック 『孤独の科学』河出書房新社 2010
山崎丈夫 『地域コミュニティ論』 自治体研究社 2009
細内信孝 『コミュニティ・ビジネス』
総理府青少年対策本部『国際比較・日本の子供と母親-国際児童年記念最終報告書』1980