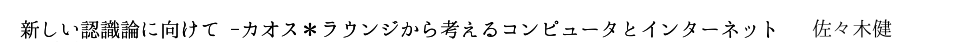
目次
序論
1章 カオス*ラウンジについて
1-1 カオス*ラウンジとは何か
1-2 カオス*ラウンジ騒動について
1-3 カオス*ラウンジのキーワード
1-4 カオス*ラウンジの美術史上の位置づけ
2章 コンピューターとインターネットについて
2-1 コンピューターとインターネットの歴史
2-2 コンピューターとインターネットの性質
3章 コンピューターとインターネットの影響
3-1 コンピューターとインターネットの影
3-2 ツールとしてから風土としてへ
4章 風土としての情報技術
4-1 風土として
4-2 風土で育まれるものについて
4-3 認識の変化と技術
結論
参考文献一覧
序論
現代に生きる私たちの生活は、いまや情報技術なしには成立しない。様々な情報をデジタル化しメディアを介して送受信することで、私たちの生活は従来に比べ格段に効率的になっている。またここ日本においては、3種の神器と呼ばれた家電製品をはじめとする機械技術の登場によって余暇が生み出され、それが新たな文化を生み出してきたことを、幼いころから学校教育の場で教わり続けてきたはずである。新しい技術は単に生活にかかるコストを下げるだけでなく、それによって新しい文化をつくりだしたり、その手助けとなっているといえる。
しかし私たちをとりまくこの情報技術に対して、生活を効率よくするだけの道具という認識が主流になってはいないだろうか。情報技術は従来人の手による作業だったことを、機会が置き換えているだけではなく、人の手では成せないことを肩代わりしている点で従来の道具と一線を画している。また情報技術がもたらす利便性は、その利便性によってそれまでの営みを忘れさせてしまったり、情報技術の本質を覆い隠しているようにもみえる。
技術が私たちの思考様式や価値観に、何らかの影響を与えることは歴史が証明している。かつてグーテンベルグが活版印刷を発明したことと、ルターが宗教改革を唱えたことは決して個別的な事象ではない。また写真技術の登場とモダニズムの絵画の発展も、やはり相互に関係した事象である。では私たちを瞬く間に包囲した情報技術は、私たちに一体どのような変化をもたらしているのだろうか。
ここ数年活発に活動し、物議をかもしているカオス*ラウンジというアーティストグループがいる。彼らは自らを「CHAOS*LOUNGEはネットの中で、主にアーキテクチャと呼ばれるインフラストラクチャーの変化と共に存在していた。」とし、その活動の背景にインターネットをはじめとする情報技術を提示している。この主張は後に彼らと世間との対立につながっていき、これまでの価値観を揺さぶるような騒動を引き起こす事となった。
このことはなにも彼らだけの問題だけではない。ファイル共有ソフトのwinnyの開発者が逮捕、起訴された事例をはじめ、従来の価値観、倫理観では判断できない状況が日々新たに生まれている。 これからさらに噴出するであろう新たな問題に対し、私たちはこの高度に情報化された環境で日々変化していく認識を分析し、新たな世界観が現れつつあることを認識していかなければならない。
アートには、私たち人間と世界との関わりを知覚可能な表現に変化する側面がある。その意図された使い方にのっとっている限り、便利な道具としてしか認識できない技術も、アートとして扱われることで、その新たな面を認識されることができる。 カオス*ラウンジの面々もまた、インターネット上で育まれた習慣、文化をアートの世界に持ち込むことで、その奇異さや独自性を明らかにしていった。
芸術表現の変遷は、その表現方法の追求の歴史であり、つまるところ技術の歴史とパラレルな歴史として捉える事が出来る。本論文では情報社会の中で生まれたアートを、その前提となる技術について分析し、 その情報技術を前提とした社会と、それに伴い変化しつつある私たちの世界観の変化と今後起こりうる問題に対して、思索の糸口になりえる考えをつくることを目的としている。
コンピューターをはじめとする情報技術やインターネットを利用したアートであるメディア・アートやインターネット・アートは、その登場からある程度の時間がたっているにもかかわらず、私たちにはまだ語る言葉が見つけられていないように思う。それは表現の様式や作品の内容の変化の要因として、技術の変化というものが軽視されていることに由来しているように思える。これは人の想像力が技術によって規定されるということを言いたいわけではなく、技術に対してより正当な評価と分析をしようというものである。
よって本研究は歴史的な出来事や美術史の変遷のなかで情報技術とアートを位置づけようとするのではなく、技術史的な観点からそれらを語る言葉を見つけていくことを主眼に置いて進めていきたい。
カオス*ラウンジが引き起こした騒動は一般に、その態度や方法の善悪が問われることが多い。しかしこの騒動はアート作品を制作する際の倫理や認識しておかなければいけない事柄として捉えるだけでは扱いきれない問題であり解決することはできない。この問題はより広範にわたる議論の元となるものであり、ひいては私たちの世界観や価値観に揺さぶりをかけるだけの問題をはらんでいるからである。
彼ら自身のスタンスや思想に着目してことの善悪を判定するという議論から、彼らの活動の原動力となっている情報技術に着目してその性質から彼らがなぜ一般の人々と異なる思想をもつにいたったのかを分析することで、その問題にたいして何らかの回答を得られるのではないかと思う。そして新しい価値観や認識論を作り上げりあげたいというのが本研究の動機である。私たちは歴史の重大な移り目に立ち会っている。そのことから出来る限りのことを語りつくしておくことが、今後重要になるのではないだろうか。
1、カオスラウンジについて。
1-1 カオス*ラウンジとは何か
カオス*ラウンジは展示会の名称と、集団を指す名称の二つの意味を持っている。 展示会としてのカオス*ラウンジには前身となる「ポストポッパーズ」 という展示会が、2008年に開催され、現在活動は長期の休止期間に入っている。 それには代表である美術作家の藤代嘘が後述するカオス*ラウンジの活動に専念してきたことと、参加作家の時間的な都合がつきづらくなってきたことを理由としてあげている。
ポストポッパーズはネット上で作品を発表している作家たちを集めたオフ会という形で企画されグループ展のような形式で作品発表を行っていた。ポストポッパーズという名称の指す通り、参加した作家の多くはコラージュやデータの再加工などを多用し、作品のモチーフも日本の漫画的なものが数多く用いるポップ・アートをほうふつとした方法、内容の作品が多く存在していた。主催である藤城嘘によれば、ネット上で半ば匿名の作家として作品制作を行うポストポッパーズの参加者たちの類まれな創作意欲と製作量に着目し、新時代のアートとして世に問いたかったという意図があったという。
2009年以降、美術批評家の黒瀬洋平の参加とともに、展示会とグループとしてのカオス*ラウンジの活動が本格的になった。また様々な分野との軋轢が生まれ始めたのもこの時期からである。現在中心的な役割を果たしているのはポストポッパーズを主宰していた藤城嘘、作家の梅沢和木、キュレーターの黒瀬洋平の3人であり、それ以外のメンバーは展示会のコンセプトやタイミングによって流動的に変化しているがこの3者は常に中心的な役割を負ってきた。
カオス*ラウンジが黒瀬洋平とともに活動するようになってからの活動の指針となっているのは、2010年に発表された「カオス*ラウンジ宣言」である。彼らの指針となっているこの宣言文から、彼らの思想とその制作の特徴を確認していく。
宣言文の冒頭において、彼らは「ゼロ年代に入って、ますますわれわれの生活を変容させた情報化の進展は、あろうことかアートにおいて、日本と世界の格差を埋めるものとして、きわめて楽観的に解釈された。」としている。
ここで言われる日本と世界の格差とは、海に囲まれた島国という空間的な意味での断絶と、それに伴う情報伝達の「速度」を指していると思われる。しかし彼らにとって情報化の進展がもたらした影響は、空間的・時間的な制限を乗り越えるものとしてではなく、より深刻な変化をもたらしていると考えられていた。つまり単なるインフラとしてではなく、より私たちに影響を与え、なおかつそれがかならずしもメリットであるとは限らないという問題意識を彼らは共有していたと言えるだろう。
また続いて「(中略)アーティストたちは「物」に充足することで、「情報」から目を逸らし、ナマな文化の営みに身を晒さない。無根拠なアートの神秘性によって身分を保障されると同時に、小器用な職人として囲い込まれている。」と宣言している。この部分は彼らにとって、「物」ではなく「情報」がより「ナマな文化の営み」として捉えられていることをはっきりと表している。ここでは彼らが、かつてベンヤミンが『複製技術時代の芸術』において提示した礼拝的価値と展示的価値のうち、後者により重きを置いていることを示しているだろう。技術革新によって隠匿、占有されることによって価値が生まれていた美術作品が多くの人の目に触れることになって以来、ベンヤミンは展示されることによって価値をもつ美術作品の登場を語ったが、さらに状況が進んだ結果、「物」という固有のものにこそ価値があるという理論への揺り戻しが起きていることを指摘している。
ている。 そして宣言文の山場ともいえる締めでは以下のように語っている。 「CHAOS*LOUNGEはネットの中で、主にアーキテクチャと呼ばれるインフラストラクチャーの変化と共に存在していた。そこは常に、膨大に、匿名的な想像力がうずまき、作品未満の作品、コンテンツ未満のコンテンツが現れては消える場所であり、にもかかわらず、作者性に目覚めてしまった有象無象の集う場所である。増殖を続けるアーキテクチャは、アートの神秘性を認めない。そこでは、すべてが可視化され、分類され、操作可能となる。内面などない。知性も感性も、すべてはアーキテクチャ上で、システマチックに組み立てられてゆく。人間の内面は、アーキテクチャによる工学的な介入によって蒸発する。(中略)しかし、彼らは、アーキテクチャによる工学的介入の結果に対し、さらに人為的に介入を試みるのである。彼らは、アーキテクチャによって、自動的に吐き出される演算結果を収集する。そして、自らがひとつのアーキテクチャとなって、新たな演算を開始するのだ。単なる「情報」でも「物」でもない、アーキテクチャ時代のアート、すなわち、一〇年代のアートとして。」
ここで繰り返し用いられている「アーキテクチャ」とその「工学的介入」とは一体何なのだろうか。この宣言文が書かれる2年前の2008年、情報社会学者の濱野智史によって『アーキテクチャの生態系』という書籍が出版されている。この書においてアーキテクチャとは、なんらかの情報が扱われる物理的、仮想的な場を指すものとされる。それは現実の建築物と同様に、私たちに対しなんらかの無意識的な介入を行う。介入にはキーボードの破損を防ぐため、頻出するアルファベットを比較的押しにくい位置に配置するといった物理的なものから、扱える情報量や質を制限することで特定のコンテンツを優遇し育てるといったソフト的な介入方法が考えられる。アーキテクチャとは、この二つの面を包括する人工的に作り出された環境を指す概念である。高度に情報化された社会では、その情報をいかに扱うかが重要とされる。そしてその扱い方を無意識に規定するものとしてアーキテクチャが重視されるのである。
後者の「工学的な介入」は先述したアーキテクチャの作用である、無意識的に人や情報の在り方や扱い方を規定することを想定しているのだろう。例えば音楽をエンコードしyoutube上にアップロードする際、YouTubeの許可するデータ量に収まるよう音質や長さが圧縮されるなどといった具体的な事例が考えられる。アナログの音波や絵画であれば、場所を移動するだけでその場に応じて都合よく圧縮したり小さく縮小するなどといった現象はおこらないが、情報化されることによってアーキテクチャがそのような編集を容易にできるようになる。
彼らの問題意識の根底には、ネットを用いて何かをするにあたって必ず情報化というプロセスを踏むこと。そして情報化したからには利用しているインフラ(アーキテクチャ)の介入を免れないこと。そして情報化されたからには数学的な操作が可能になり、原理上自由に容姿を修正したり、声を偽ったり、性別すらも簡単に操作できるようになるという認識が存在している。
しかし一方で内面が蒸発するといった、情報化によってものの固有性や精神的な何かが失われてしまうことも自覚しているようにみえる。これはオリジナリティなどなく、すべては機械的に組み合わせによってできていることを示しているのではなく、それに対してより固有の何かを求めている姿勢ではないかと考えられる。
この認識が正しいかどうかはさておき、彼らはこのような認識の下で製作、展示を行い、議論を巻き起こしてきたとして、では実際に彼らの活動がどのような問題を引き起こしたのかを確認したい。
1-2 カオス*ラウンジ騒動について
彼らが引き起こした騒動の一部は、主催者の不手際が招いたものも多く一概に重要視できるわけではない。しかし本研究にあたって非常に興味深いいくつかの問題が指摘されていたことも事実である。
まず彼らに対する批判の中でもひと際大きく目立ったのが著作権と商標権に関わる問題である。カオス*ラウンジの中心的な作家である梅沢和木の作品に多数の企業ロゴや既存のキャラクター、あるいは二次創作イラストがコラージュの元として使用されていたことが、使用されたイラストの著作権者によって指摘され、商品として流通していたものが自主的に回収となった事件である。これを皮切りに、コラージュは創作の方法として妥当なのかという疑問提起がなされた。またコラージュの元となった作品の著作権者が精神的な被害を受けるという事態がおきるなど、火種は様々な形で広がっていき、梅沢和木に対する脅迫めいた書き込みがネット上で散見される状態となった。
コラージュという手法や挑発的な宣言文によって、何らかの批判が起こることは彼らにとっても容易に想像できることであったはずである。しかしその後の対応を見る限り、脅迫めいた批判を繰り返す人間が少なからず現れるという事態までは想定していなかったようにみえる。ではなぜそういった人間の出現を予想できなかったのか。またなぜそういった人間が出現したのだろうか。
彼らはなぜ批判にさらされながらも既存の倫理観を無視した行動をとったのか。それは彼らにとって、インターネット社会は既存の社会とは異なる原理原則で成立したオルタナティブな世界であったからだ。彼らがアイデンティティとしているネットの宇宙では、私たちが真理であると経験的に判断している原理が通用しないのではないだろうか。こぼれた水はコップにそのまま戻ることは決してないが、シミュレーションで成り立つ情報空間の中では簡単に元に戻す事が可能であるように、異なる原理原則で成り立つ世界に対し、地上の物差しで分析することは困難なのではないだろうか。
彼らは何度もインターネット上に点在する情報は誰のものでもないということを繰り返してきた。実際にはウェブサイトやそこで表示されるデータにはそれを作った人間が存在しているはずであるが、なぜそのような主張をとってきたのだろうか。第一に、確かに作者を軽視、あるいは作者の存在自体が全く意識されない環境があることは事実である。署名を入れる文化の内インターネット上では、はっきりと主張してもそれが誰によるものなのかはよほど熱心に探さない限り知ることはできない。また現実世界と違い簡単に複製が可能だという点も作用しているように思われる。インターネット上のデータの作者が分かりにくい理由の一つに、簡単な操作で無限に複製、転載が可能であることからくるソースにたどりつくことの困難さが挙げられる。そしてこのソースをたどることの困難さとともに、ソースが不在という事態も簡単に起きるのがインターネットである。現実ならば発行所や作者は死なない限りいなくなることはないが、インターネット上ではパソコンを買い変えたり、HPを閉じてしまったり、簡単なことで発信源にたどりつくことができなくなってしまう。
この宣言文を理解するためには、このような、彼らがよるインターネットという場の原理について分析し、その上で語る言葉を作らなくてはならないのである。
1‐3 カオス*ラウンジのキーワード-メディア、インターネット、コンピューター、アーキテクチャ‐
カオス*ラウンジがなぜアーキテクチャというキーワードにこだわるのか。それにはまずそれが存在しているインターネットとそれを運用するコンピューター、そして私たちとそれとをつなぐ媒体(メディア)について理解する必要がある。
前節でインターネット特有の状況についていくつか説明したが、なぜそのような状況が生まれるのかについても触れながらカオス*ラウンジが多用するキーワードについて補足を行いたい。
はじめに、インターネット空間という場は存在しないということ確認したい。こコマでの文中でも使い、普段からも意識せずに「インターネット上では」という表現をしがちだが、インターネットそれ自体は単に情報の流通の関係性でしかない。しかし私たちはインターネットを場として想定している。それはなぜだろうか。
それにはインターネットと私たちを結びつけるメディアが大きな役割を果たしている。元々なんらかのデジタルなコードがまず存在し、人が理解しやすいような視覚的表現へと変換しているものが近年のメディアである。このコンピューターをはじめとするメディアは、従来のタブローや布、紙のようなものと区別され、ニューメディアという言葉で分けられてきた。私たちは直接流通している情報を目で見て理解することはできない。そこで必ずメディアによって何らかの形で表現し、それについて考えることを可能にしている。よって私たちはそのデコードの仕組みに理解や考え方を左右されていると言ってもよい。例えばあるデジタル写真を複数の人間に送ったとき、その受け手が使っているスクリーンの質によってそこで目にする画像の鮮明さは変化する。そのときより鮮やかなスクリーンを使うものにはその場の情景がまざまざと伝わるのに対して、不鮮明な古いものを使っている人間は映っているものを判別し、あとは想像にゆだねるしかない。このように、まずここでメディアがもつ、情報を私たちが目にする際の影響を想像することができるだろう。
またインターネットは情報の流通のシステムでしかないため、インターネットについて語ることは情報のインフラアーキテクチャを語ることに他ならない。私たちが舗装された道を通って歩くように、情報もまた人によって設計されたインフラを利用する。そのため私たちが靴を履くのと同じく、情報もそのインフラを通るため適切な形にコード化され流通している。デジタル情報とは何らかのアナログ情報をある計測方法で離散数的に表現したものである。そして計測方法はそれによって得られた情報が運用できるよう、インフラに配慮した計測方法になる。すべての物は様々な情報を内包した存在である。それをどのように、どこまで情報化するかが情報存在の在りようを決定するのである。
つまりどのような方法で情報化するかということが、情報がどのようになるかを決定しているため、情報存在について考えるにはそれがどのようなアーキテクチャ上で情報化されたかを検討する必要があるのだ。
私たちが情報存在を手に取ったり肌で触れて確認することが出来ない以上、何らかのメディアを介して確認するしかない。しかしそのメディアはそれぞれ独自のシステムで私たちに情報存在を表現しているため、私たちは情報存在の認識にメディアの設計思想から無意識の影響を受けている。またその情報存在もどのようなメディアを介して情報空間の中で情報存在として成立したかによって姿かたちをかえていく。もとは同じ物質だったものが、異なるレンズや画像処理システムをとおることで全く別の物のように表現されることが多々ある。
このような状況があるため、彼らカオス*ラウンジはメディアであるコンピューター、インターネットやインターネット上のサービスをアーキテクチャとして捉え、その設計思想を顧みているのである。
1‐4 美術史の上でのカオス*ラウンジの位置づけ
彼らの活動は自ら「ポストポッパーズ」と名乗っていたことから、ポップ・アートの流れをくんでいることが分かる。中心的な役割を果たしている作家たちは、程度の差こそあれコラージュを多用し、商業的なアイコンを多く作品にとりこんでいる。用いられるイメージは、キャンベルスープの缶やマリリン・モンローから、Googleやyahooのロゴやアニメのキャラクターへと変化しているが、本質的には共通したものを表現しようとしているようにみえる。
またその後の1980年代に流行したアプロプリエーションやシミュレーショニズムと呼ばれるアートと直接的な関係を持っている。シミュレーショニズムはさまざまな方法のアート作品を指すやや広い概念ではあるが、その中心になっているのはシミュレーション・アートと呼ばれるものである。シミュレーション・アートにもまた様々な形式が存在するが、美術批評家で『シミュレーショニズム』の著者である椹木野衣によると「その中核となるのは日常的な風景の共同体的な記号をリメイク/リモデルすることによって意味論的に脱臼させる立場」 とされている。
日本を代表するシミュレーション・アーティストは森村泰昌である。彼はゴッホの作品に自分を滑り込ませる手法にはじまり、ハリウッド・スターや世界的なミュージシャンに扮して(シミュレーションして)写真をとることで、彼らがもつ記号的な意味を脱臼させている。
カオス*ラウンジの手法は方法的にはシミュレーション・アートが行っていたサンプリング、カットアップ、リミックスといった手法と共通している。彼らはインターネット上からプリントアウトした画像を水に浸したり、破いて製作を行ったり、解像度や色みの調整等を行い制作していたこともある。また様々な場所から画像データを持ち出し、一つの画面で並べるのではなく融合させて一枚の絵画として仕上げている。これもまたモチーフをシミュレーショニズムと共有しているだけでなく、その機能も盗用してきた記号の意味を脱臼させ、記号的な意味に隠されてきた何かを明らかにしようとする試みという点でも共通している。
これらをはじめ、カオス*ラウンジは宣言においてこれまでのアートと断絶し更新する存在であることを強調しているものの、美術史の中に位置づけることはそれほど難しいことではないように見える。むしろこれまでの美術史を顧みれば、その出現は容易に想像できることであったように思う。ではなぜここまでのバッシングを受けるにいたったのか。それは美術史に彼らを位置づけることでは問題を扱うことはできない。なぜなら彼らが引き起こした騒動は、芸術や美術とはなにかについての問いには決してならなかったからである。確かにある一面では美術史の中に位置づけ語ることが出来る側面ももっている。しかしこれまでの他のアートと一線を画しているのは、騒動がアートという枠組みではなく、一般の社会生活の中での倫理観や世界観についての問題意識によって語られることとなった点である。
確かにアートもまた社会の一部として存在している。いわゆる「芸術のための芸術」という立場が20世紀初頭に西洋美術史の中で現れたが、その後の機械技術の発展とともにバウハウスや「デ・スティル」の生活と芸術の統一という運動が現れて以来、生活と芸術をより結びついたものとして捉えていく歴史の観点が重要となってきている。
彼らの騒動を分析するに当たっては、美術史的な文脈を用いるのではなく、機械技術と私たちの生活史的な文脈からアプローチすることが適切ではないだろうか。そこで次章では、私たちの生活の基盤となっている機械技術の歴史と生活の変化についてまとめ、分析を試みていきたい。
2章 コンピューターとインターネットについて
2-1 コンピューターとインターネットの歴史
ここまで現在使われているインターネットについての分析をすすめてきたが、ここでさらにそのインターネットがどのように成立したかについて話を進めたい。現在習慣化しているインターネットの使い方について一体どのようにそれがなりたってきたのかを分析することで、より原理的な影響について考えられるのではないかと思う。
そこでまずはインターネットを使うために必要なコンピューターの仕組みを振り返ってみたい。
コンピューターの歴史は思いのほか長く、18世紀から19世紀にかけて活躍した数学者であり分析哲学者でもあったチャールズ・バベッジ(1792-1871)が、既にプログラミング可能な計算機の設計を行っている。彼の設計した計算装置である階差機関は様々な理由から当時実際に組み立てられることはなかったが、1989年に実際に製作され機能することが確認された。また彼はその後つくられるチューリング・マシンと同様の方法で入出力を行う分析装置をも設計している。
バベッジが生きたその当時、まだ計算機として数字を扱うために設計されたコンピューターだが、第二次世界大戦時チューリング(1912-54)によってコロッサスと呼ばれる暗号解読のためのコンピューターが製作された。コロッサスはパンチングされた紙テープによって入力された情報を解析する機能を持っていた。これによって算術のために用いられてきたコンピューターが、文字を扱うことも可能だということが初めて実証されることとなった。
コンピューターはこのような変遷をたどり進化し続け、現在ではイメージや音、文字等を同時に扱うことができるマルチメディアへと進化した。その後コンピューターは発展を続け、1984年にMacが開発されると、劇的にGUI(Graphical User Interface)が浸透した。それまで主に文字を入力することでコンピューターに指示を出していたものが、イメージを操作することで指示を出すシステムへ転換された。それはかつて数字を扱うものであったコンピューターが、文字を扱うようになった変化と同様に、文字を扱うものであったコンピューターがイメージを扱うものとなった瞬間であった。
続いてインターネットの歴史だが、こちらはより短い期間に急激に発達した技術である。そのはじめとされるのは米陸軍のヴァーニヴァー・ブッシュ(1890-1974)が構想した「Memex」というシステムであるとされている。Memexは不特定多数の人間が、様々なマイクロフィルムを同時に閲覧し、編集できるというシステムであり、今日教育のツールとして再考されている。この同時に複数の人間が同じものを閲覧し、書き込み、それにたいしてさらに書き込みを加えるというシステムは、今日のインターネット上でのコミュニケーションときわめて類似している。
現在のインターネットに対し、直接的な影響を与えたのはテオドール・ネルソンが構想した「ザナドゥ」というシステムである。ザナドゥとはテキスト、音、イメージのデータが相互につながりあうことで形成される仮想の場であり、繋がりあったデータ群を「ハイパーテキスト」や「ハイパーメディア」という言葉で表現した。ネルソンが構想したザナドゥはいまだ実現には至っていないが、単方向にデータを結びつけるWWW(World Wide Web)が地球規模のハイパーテキスト計画として実用化されている。WWWは元々研究所間の情報の移動にかかるコストや時間的なずれを解消するため、研究情報を物理的な拘束から解放し、非中心化することを目的としていた。よって情報の双方向性や、閲覧の際に場所を制限されない自由度の高いアクセス方法を実現する方向に向かったことは必然であったといえる。
このコンピューターとインターネットの歴史は、それらのもつ性質と深く関係している。はじめに扱ったカオス*ラウンジの騒動だが、このようにインターネットやコンピューターの起こりを振り返ってみると、彼らの活動もまた彼らの主張するインフラアーキテクチャによって規定されていることがわかる。つまり彼らの独自性であった作者を無視した転載や複製の利用は、そもそもインターネットがそういった行為を指向して作られたシステムであることから必然的に生まれるものであったといすることができるのではないだろうか。そして彼らはそれに対し無自覚ではなく、自覚していたがゆえにあえてその「工学的な介入」を一旦は受け入れたのではないだろうか。
次節ではこれらの歴史的な背景が、現在私たちが利用しているコンピューターとインターネットの性質に対しどのように関係しているのか。そしてその性質が私たちとどのように関係しているのかについての考察を深めていく。
2-2コンピューターとインターネットの性質
私たちと技術の関係を考える時、その技術の性質を考えることがまず重要になる。なぜなら私たちは道具を扱うと同時に、その道具に合わせて変化をする性質を持っているからだ。このことはある道具を使いなれてくるにしたがって、より効率的にその道具を扱えるようになることから経験的に理解できる。また逆に私たちに使いやすいよう道具の側も作りかえられていく。これも今日にいたるまで様々な道具を利用して生活してきたことを顧みるまでもなく自明のことである。
では計算機からイメージの操作機へと発展してきたコンピューターと、それを用いて情報の非中心化を目的として構想された現在のインターネットはどのような性質を持つのだろうか。
まずコンピューターからみていく。ニューメディア研究で知られるレフ・マノヴィッチは、自身の著書である「The Language of New Media」の中でニューメディアの原理として5つの特性を挙げている。
ひとつは「数字による表象」である。これは一般にニューメディアと呼ばれるコンピューター一般は、離散数的なものしか扱えないことに由来する。アナログ情報は、一度デジタル情報に変換されなければコンピューター上で扱うことが出来ない。つまりどんなに高精細なイメージを表示するディスプレイとコンピューターがあったとしても、それがコンピューターによって表示されている限り原理的には数字によって表象されているといえる。表示されるデータが精密になるほど見えにくくなるが、コンピューターが数字を扱う機械として開発され進化してきたことを振り返れば当然の原理である。
二つ目は「モジュール性」である。ニューメディアが扱う表象は部分に分割でき、その部分が組み合わされて構成されているという。映像は光の明滅に関する情報や、音の高低や有無に関する情報などが組み合わされて構成されている
3つ目と4つ目は「自動性」と「可変性」である。両者はともにニューメディアを用いた表象が、数字によって表象されることと、組み合わせで構成されることに由来する。物理的に筆を走らせ絵を描くのと違い、コンピューター上で作画を行う際には様々な操作が背景で自動に行われている。また意図的にある動作を自動で行うように指示することもできる。
また表象がデジタル情報の組み合わせで成り立っていることから、その組み合わせ方を変更することで簡単に操作することが出来る。よって常に更新され続ける可能性を持っているという。どちらもアナログなメディアでは不可能なため、ニューメディアと呼ばれるものの特性とすることができるだろう。
そして最後に「トランスコーディング」と呼ぶ原理がある。これは北野圭介によって「超コード化」とも訳されている。これはコンピューターが様々な場面で使われていくにあたって、様々な事象をコンピューターが認識できるようエンコードしていくと同時に、コード化された情報が出力され私たちの世界を飲みこんで行くという指摘である。これは従来コンピューターを利用するために考案されたデータベースの構築方法が、私たちの生活の中にも浸透し、様々な形で応用されていることから理解できるとしている。
ではインターネットの特質とは一体何なのだろうか。今日のインターネットを考える上で重要なメディア論者にポール・ヴィリリオ(1932-)とマーシャル・マクルーハン(1911-1980)がいる。ヴィリリオは直接インターネットを語ったわけではないが、彼が行った映画を速度の問題として分析する手法は今日のインターネットに対しても有用である。早稲田大学教授の長谷正人は、映画がリュミエール兄弟によって発明されたのち、各地に撮影者を派遣し旅行記を撮らせ上映したことが、映画が速度の問題とみなされる証明としている。つまり、映画は高速で別の場所に私たちを移動させるメディアとして捉えられるというのである。この観点から考えると、インターネットの特質もまた速度にあるといえる。本来情報の移動速度の高速化を目的に作られ、現在では様々な用途に用いられているが、インターネットは私たちの世界を加速させているといえる。しかし映画における加速とは異なり、常にあらゆる場所で同時に同じものを表示することができるインターネットは、ある情報の移動や速度という観点から、新たに別の場所という認識を私たちに与えている。それがマクルーハンの提唱した地球村の概念である。これは高速の電子通信技術によって国境や地理上の断絶を飛び越えたコミュニケーションが可能になったことで、地球を一つの村のように扱うことができるという概念であったが、現在ではおもにインターネットそのものを指す語として用いられることが多い。ここで着目するのは、インターネット空間というものを想定する想像力である。一次的なアナログ情報をデジタル化し、信号として送信されたものを受信して表示するという一般的な情報のやり取りをする際、私たちはインターネット上から「落とす」といった表現をすることがある。それはインターネット空間的なものが存在し、その空間から自由に情報を引き出したり、逆にしまったりできるという発想である。
作家の東浩紀はこの二つのインターネット理解を速度=距離的な理解と空間的な理解として整理している。 彼は「サイバースペースはなぜそう呼ばれるか」の中で、ヴィリリオ的なインターネットに対する理解を「たとえば1930年代にハイデガーは、ラジオを例に挙げ「あらゆる種類の速度の高騰は遠隔性の克服を目指す」と記している。(「存在と時間」第23節)彼の哲学にとって、テレメディアは世界の近さを保証する装置、「遠隔性の除去」の過激化した形態にすぎない。この考えは航空機とラジオを同列に扱うものだ。(「世界像の時代」)」 と、ハイデガーから続く一連の流れとして整理した。
また空間的な理解に対しては、その伝統的なメディア理解を踏襲しつつも、「たとえば、1970年代イタリアのアウトミア運動、とりわけ自由ラジオ戦略が、メディアに新たな公共空間を見出す発想で支えられていたことは広く知られている。また磯崎新が指摘するように、1960年代にはメディアに新たな建築空間の可能性を探る試みが出現している(『建築の解体』)。」と同世代の議論を参照しながら「マクルーハンの「地球村」も、1960年代から1970年代にかけて生じた一連の流れ、「メディア空間」という新たなイメージの浸透/拡散の動きの一例だと考えられる。」 としている。
こうした二つの流れのうち、前者はイタリアで未来派が絵画的な表象にいかに速度、運動ををもちこむかという指向に関係している。ジャコモ・バルラの「綱で引かれた犬のダイナミズム」でいかに移動する物体を描くかという指向性に顕著なように、未来派はメディアがもたらす生活の変化の未来について、それが速度という問題をもっていることを察知しその観点から取り入れて行ったといえる。
後者の空間的な理解は、同時代のアートの中でも特にシミュレーショニズムに顕著に表れている。シミュレーショニズムの作家が現実をシミュレーションし意味論的に脱臼させるという発想は、まず現実とは別の空間があることを想定しなければならない。それはメディア空間という理解によってもたらされたものであると言える。
これらの時間と空間という二つのメディアに対する観点のうち、前者は私たちの時間の質に対して影響を与えているのに対して、空間的な理解は全く別であったり、もしくはより空間を広げるような想定するような働きを持っている。特に空間的な問題として捉えることは、より現在の状況にマッチしているように思える。
次節ではマノヴィッチのニューメディアの原理として提示された五つの原理と、インターネットの空間性という理解がどのように私たちと結びついているのかについて検討してみたい。
3章 コンピューターとインターネットの影響
3-1 コンピューターとインターネットの影響
2章でコンピューターとインターネットの歴史、それらの特徴について整理したが、これらは一体私たちの認識にどのような影響を与えているのだろうか。再びカオス*ラウンジ宣言と照らし合わせながら検討してみることにする。
私たちがコンピューターで自分たちのことを表現する時、その雰囲気やまとう空気を使うことはできない。私たちは必ず自身の年齢や身長、肌の色合い、目頭から目じりの角度など、様々な数的な情報へ自身の身体を情報化することでメディア空間の中に自分を映しこむことができる。そして情報化された私たちは、コンピューターによってシミュレーションされメディアを介して表象される。
この仕組みがカオス*ラウンジの作風の原点にあり、またその批判者との確執の原因になっている。宣言文中に「彼らは、アーキテクチャによる工学的介入を、一度は徹底的に受け入れる。アートに神秘性などない。人間の知性も感性も内面も、すべては工学的に記述可能である。」 とあるように、彼らはアーキテクチャと呼ぶコンピューターによる工学的な介入、つまり情報化とそれを表示するメディアによる操作を全面的に受け入れているのである。それは単に概念上の戯れとしてではなく、実際に彼らは自身の画像をフリー素材として扱い、ネット上で編集されていた。
彼らが人間の知性、感性、内面といった従来個人が持つ尊いものとされてきたものを、すべて工学的に記述可能であるとする発想の背景には、こうした情報化を受け入れていることがあげられる。彼らが意識的にか直観的にかはわからないが、すべてが情報化されるという理解はマノヴィッチが提唱した「トランスコーディング」という原理と共通している。
もういちどトランスコーディングについて整理する。トランスコーディングとは「超コード化」とも訳されているように、ある一部に関してコード化が起こるのではなく、すべてがコード化されていく現象である。実際に、街中に監視カメラや計測器を設置することで生活者の情報を外側から読みとり個人情報として記録してくことも、一部自治体では活発に行われている。
従来であれば、個人情報化がもたらすのは均質な人の記述に対する嫌悪感や、権力のプライベートへの介入などといった反体制的な運動を引き起こしてきた現象だが、カオス*ラウンジは一度それを徹底的に受け入れるとしている点がそれらの態度と一線を画している。
では工学的な介入を徹底的に受け入れるとどうなるのだろうか。それは彼らが用いるもう一つのキーワードである「匿名」から読みとることが出来る。彼らが用いる匿名、あるいは匿名性とは、インターネットを使う際に起きる特有の現象である。実際に面と向かい合うコミュニケーションや、物体を伴う芸術作品にはその人が常に関係づけられている。彫刻や絵画には手の痕跡が残っているし、面と向かっていれば言葉が口から発せられる瞬間を目にすることができる。しかしインターネット上でのコミュニケーションや作品制作は、そういった人の痕跡を残さない。そのものと実際の人との結びつきを解消する働きをコンピューターが持っているといえる。
これは私たちがインターネットやコンピューターと触れ合うときにのみ現れる現象だが、その触れ合う機会がより拡大していることに問題がある。現在どの国でも、自国の情報環境をより広く高速にしていくむきが主流である。あらゆる場所から常にインターネット空間にアクセスできるインフラの構築を目標に、あらゆるものが電化されインターネットの一部として機能している。
この情報環境の充実とマノヴィッチの提唱したトランスコーディングの原理によって、私たちの世界のコード化はより進み、カオスラウンジ的な想像力の元となっているのではないだろうか。そしてこの想像力は彼らにしかみられないものなのだろうか。
この情報技術が新しい空間として世界の覆いかぶさっていく状況について次節でより分析する。
3-2 ツールとしてから風土としてへ
金槌や筆記用具といった道具に比べ、インターネットなどの情報技術は私たちに空間的な認識を与える。それにより私たちは従来の道具と人間の関係性という問いの立て方から、風土としての情報環境と人間の関係性という問いの立て方に思考を転換していかなければならない。
従来の道具と私たちの関係は、物と人とがある瞬間にのみ接点をもって関係するようなものであったが、インターネット、コンピューターはそれ自体が自立した空間をつくりだしている。正確には自立した空間かのような錯覚を私たちに与えているとしたほうがいいのかもしれないが、そういった空間の中にいるように感じさせることを無視することはできない。
ドイツの哲学者のヴィレム・フルッサーは、自身の『写真の哲学のために』の中で、「情報を与えること」 が道具の働きであったとしている。続いて「以前は道具が変わるべきものだったのに、それ以降は人間が変わるべきものになり、機械の方が定常的なものになりました。以前は、道具は人間の働きの中で機能していたのに、その後は、人間が機械のはたらきの中で機能するようになったのです。」 としている。
このハイデッガーから続く、産業革命以前に存在していた道具と、産業革命以後に生まれた機械化された技術という区分は、当時から人の側が変わるべきものになっていることを指摘していた。ここではさらにその状況が進行したといえるだろう。
この現状を表すにあたって、従来のように道具や技術としてコンピューターに接するのではなく、より定常的でより私たちを囲むような表現に置き換えてみたい。まずインターネットはなんらかの空間性を有しており、そこではコミュニケーションが可能で、情報の送受信ができる。またその空間は均質なものではなく、言語やつくられる文化によって様々な景色を持っている。
そういった条件を考えると「風土」という言葉が適切ではないかだろうか。風土とはもともと単に環境を指すのではなく、その土地がもつ様々な特徴やそこで育った文化的な気風を内包した概念である。インターネットにもある種のそうした風土性を帯び始めているのではないか。
ここでいう文化的な気風とは、近年盛んにさけばれている日本の情報環境のガラパゴス性にみてとれる。日本ではimodeをはじめとする様々な情報環境が独自の発展を遂げてきた。このことを英語圏の情報環境と比較して閉じているという言説である。しかしこのガラパゴスというは実際のガラパゴスと違い、日本に限ったことではない。日本は確かに日本語という一国でのみ公用語として使われている言語でコミュニケーションをとる国ではあるが、その国独自の情報環境という点ではアメリカでもイギリスでもインドでも変わらずその独自性は存在している。
しかしインターネット空間はすべて等しく数的な情報をやりとりする場であるとみなされていることから、その独自性が際だって目立っているのである。
こうして風土として捉えることによって、この論文のきっかけとなったカオス*ラウンジの面々の社会に対する理解が生まれてくることにもつながっていくのではないだろうか。つまり彼らが生きている世界と現在一般に人々が実感している世界は全く同じではなく、やや違った世界なのではないだろうかということである。それは単に主体の数だけ世界があるということではなく、世界そのものが変化しているということである。そうであるならば、彼らが起こした行為は彼ら独自の物ではなく、今後さらにおしすすめられ騒動すら起きなくなる時が来るのではないだろうか。
次の章からは風土としてインターネットをはじめとする情報技術を語ることについて考察する。
4章 風土としての情報技術
4-1 風土として
風土として情報技術を捉えるということはどういうことなのだろうか。例えばイヌイットの人々が持つ雪に対する表現は私たちのそれに比べてはるかに多様である。それと同じく、私たちは情報技術という空間によって、従来よりも多くの表現を獲得することになるだろうし、いまでも常に「バリ3」などといった造語は生まれ続けている。
何かを分析する際に、その問いの原因を背景に求め、その背景として情報技術を扱うこと。 これによって2章で取り上げたレフ・マノヴィッチのニューメディアの原理の中にあるトランスコーディングという原理は、現在最も私たちに直接影響を及ぼしている。私たちのコミュニケーションは話し言葉だけでなく、書き言葉や数字によって成立している。また面と向かうコミュニケーションよりも、量的な面では圧倒的にメディアを介して情報の交換を行うことが多くなっている。
メディアを介して情報を得るとき、メディアの背景には入力、観測を行う装置が存在し、そこで得られたデジタル情報を私たちが認知可能な表現にするとき初めてメディアが登場する。つまり私たちは一度デジタル化された情報が、デコードされたものを認知している。これは自動的に行われ、人の意思は介在しない作用であるが、人が環境に影響され適応していく性質は過敏にこのプロセスに対して反応している。
そして、その環境は人工物であるがゆえにそれがつくられる場にその性質が由来している。原理的にはすべての情報空間は等しく同様の原理の元に成り立っているが、それとは別にそれが生まれた土地柄もまた反映している。
日本は一般的にムラ社会などと呼ばれ、「個人」という概念を自発的に育ててこなかったと言われることが多い。個人はなんらかの組織やコミュニティに所属するものとしてとらえられ、公私の区別が欧米にくらべはっきりしていないというものである。これがインターネット環境に持ち込まれると、すべての人がそのサービスの利用者という所属を得るため、より匿名性が高まるのである。
また国産のネットサービスの多くは、必ずしも利用者を特定できるようには作られておらず、利用者のほとんども現実の自分をそのままネット上に持ち込むことは少ない。韓国が国民IDを導入し、誰がネットに接続しているかをはっきりと特定する仕組みを作っていることや、アメリカでface bookが主流に使われていることなどを考えると、これもまた日本の風土に根差したものであるといえよう。
このように同じ背景と原理を持っているにもかかわらず、そこで運用されるサービスはその土地の影響を受け、それぞれ独自の形で発展をとげている。そして私たちが直接関わるのはこのサービスであり、そこから受ける影響もやはり大きい。
ではこの情報環境という風土から、どのような影響をカオス*ラウンジが受けているのかについて考えたい。
4‐2 風土で育まれるものについて
私たちの視覚は瞬時に焦点をきりかえながら外界の状態を読みとっている。そこで見たものを表現する時、私たちはなるべく客観的にいくつの、どのようなものが見えているか記述しようとする。この情報化のプロセスが、よりコンピューターのそれと近づいているのである。かつて写真の開発によって、初めて人は自分たちの視界が主観的なものであったことに気付いた。それから絵画は記録的な機能を写真に明け渡し、自分の目に映るものをいかに描くかというモダニズムの絵画へと発展を遂げた。いままさにその逆のことが起きていると言える。今起きている認知の変化は、より工学的な基準で視覚を扱う、いわば機械に身を寄せる方向への変化である。
メディア時代の認知は、ある物を見て形を形容する際、「大きなもの」や「とがったもの」という文学的な理解ではなく、何cm程度で何度の角度の物であるかという数学的な情報へ指向が変わりつつある。そうして数学的な情報を得た結果、私たちは数学的な情報はコンピューターによって操作可能であることを感覚的に理解していることから、世界に対し操作可能性を直観的に感じ取っている。
ニューメディアの原理である「数字による表象」の原理は、カオス*ラウンジでは人間の内面すらも工学的に記述可能であるという思想とリンクしている。つまり私たちが物をなんらかの数字的な情報を読みとるように、彼らには内面に対しても数字的な情報として読みとろうという認識が働いているのである。このようにして彼らはコンピューターの原理に影響され、認識をこれまでと違ったものにしている。
またインターネットの特徴である匿名性についても彼らを強く結び付けることが出来る。彼らのおこした問題の一つに、著作権者がいる作品をあたかも匿名の作品であるかのように使ったことが挙げられる。非商用の無断転載はインターネット上ではめずらしくなく、転載に次ぐ転載で、もとのでどころが分からなくなっているデータは無数に存在している。そういった状況のなかで、彼らはインターネットの原理に忠実に、すべてのデータを現実の著作者から切り離された匿名の著作物として扱った。彼らの行為は一般には思慮が足りない行為のように映るかもしれない。しかし彼らは自らが利用する空間内でできること、目指されてきたことを忠実に遂行したまでであり、ある意味では素直な行いをしたということができる。
東浩紀はこの認識の変化に対し異なる視点から分析している。彼は情報技術による認識の変化を「この変化は、単なる技術的問題ではなく、より深い認識論的な変化、インターフェイス的な情報環境を前にした新たな主体の登場をともなっている。」とし新たな主体に「インターフェイス的主体」と名付けている。
「インターフェイス的主体」とは、イメージとよばれる実際に目に見えるものと、その背景にある見えないシンボルとの差がなくなり、すべてが可視化された世界における主体とされている。言い変えるなら、本来目に見えないものであった情報が、イメージとともに可視化されているといえるだろう。彼は精神分析的な手法とポストモダン論を利用しながら背景的なものが前面化していくことを指摘しているが、これはあれのままのものを認識するのではなく、それがもつ情報を要素分解的に見出していく認識に通じるものがあるのではないかと思う。
彼の新しい主体の是非はさておき、新しい技術が新しい認識とその主体を生みだしていることは確かであるといえる。では一体どのような認識が生まれているのだろうか。それについては今後さらなる研究の対象としていきたい。
4-3 認識の変化と技術
これまで分析してきた結果、カオス*ラウンジのとった製作の手法や宣言文に垣間見られる手法は、コンピューターやインターネット技術のもつ性質と深く関係していることが明らかになった。
コンピューターやインターネットが持つ原理や歴史は、知らず知らずのうちに私たちの認識を変え、情報的な認識を生みだしつつある。またその結果、様々な社会との軋轢をこれからも生み続けるだろう。この変えられた認識とは、生活空間の一部となった情報技術の機能を十分に発揮できるように変化した認識であり、情報技術の特性に則ったものである。
私たちはいまだ自分たちの認識の変化にそれほど気付いていない。偶然何らかの形でこれまでと認識が変わっていることに気づかされるが、それまでほとんど無自覚と言ってもよい。アートには底に用いられる技術をその本来の用途から解放し、それそのものについて問うことを可能にする機能がある。単なる仕切りとしての壁でさえ、これまで壁画であったりキャンバスが飾られる場として活用されることによって、その機能が何度も検討されてきた。機械技術についてももちろんそのような効果が期待できる。
また新たな情報空間やコンピューターの原理を用いて新しい美学を構想する動きもある。美学者の川野洋は2011年に『ネットワーク美学の誕生』という書籍の中で、隠されていたものや無意識的であった認識の要因が明らかになっていくなかでの新しい美学を構想している。
またギブソンが提唱したアフォーダンスの理論にも技術による認識の変化が見て取れる。彼は環境そのものが生物にとって有用な情報を内包しており、その情報は生活体の行動によって変化し、私たちもまたその情報によって変化しているとするものである。この環境と生活体の相互作用と、環境には人が共通して理解できる情報がないほうされているという考えは特に情報技術的な考えということが出来るかもしれない。また彼の「表面」とそれによる包囲光によって知覚が成り立つという発想もまた情報技術的である。なぜなら質量を表現できないディスプレイ的なものにとって、最も重要なものは表面の状態であるからだ。
技術がもたらした認識の変化を語る際に、人をコンピューター的なものとみなす事に対する批判があるが、それは誤りである。コンピューターは人のはたらきを模してつくられることがあるし、人もまたコンピューターの影響を受け変化しているからである。これはどちらかに一方を寄せて行くという発想ではなく。相互に作用しながら徐々にその距離が埋まってきているということなのである。
これまでの分析で十分な現状分析が行えているとは思わない。しかしながら語るために必要な土壌すらもできあがっていないいま、まずはその地固めをしなければならなかったことは確かである。地固めとは自分たちが生活している空間について分析することと、その空間に順応することによって引き起こされている変化を理解することである。
結論
本論文では情報技術が私たちにどのような影響を与えているかについて、現代アート集団カオス*ラウンジを題材に考察してきた。彼らの行動は様々な倫理的、法的な問題を孕んでいたが、同時に匿名の著作者による著作物の著作権問題や、アーキテクチャという存在の指摘、インターネットとは何か、コンピューターとは何かについて根本的な問題につながる問題も数多く引き起こしてくれた。
今回はなぜそのような問題が起きるのかを明らかにするため、彼らが依拠するインターネットという空間とコンピューターという技術について考察した。そして彼らの創作物や宣言文に見られる特徴は、そのままインターネットやコンピューターの原理や特徴と相互に関係があることが明らかになった。
その結果とは、まず彼らが依拠するインターネットとは、情報の固有性や所持という意識の薄い社会であるということ。そしてそのために彼らは転載や複製を悪びれることなく活用し制作をおこなってきたことがわかった。またインターネットは本来情報の共有や脱中心化を目指して作られたものであることから、そういった使い方は一見無法な行為に見えるようで、その実インターネットというアーキテクチャによって規定されていたといえる。そして彼らの目指したアーキテクチャによる介入に対して、さらに人為的な介入を行うという試みはまだ発展途上だが、今後の大きなテーマになるだろう。
インターネットやコンピューターの原理や特徴は、彼らだけでなく、私たちも含めたその利用者の想像力、認識に多大な影響を与えている。ではどのような影響を与えているのか。それはまさに20世紀半ばに流行したサイバーパンク的な未来予想に私たちがまた一歩近づいてきていることを示している。
しかしSF小説の未来予想図とは異なる事態も同時に起きている。それはカオス*ラウンジも自覚していた、すべてを匿名の情報にしてしまうコンピューターとインターネットの原理の中でも何らかの作家性が生まれるという事態である。
そしてその場所として、かつてクラークが「幼年期の終わり」のなかで想像したような、全人類が肉体を捨て意識を共有する情報空間化していく未来ではなく、なんらかの風土性をもった環境が生まれつつあるという事態である。
このような事態に際し、私たちの変化した認識に対して新たな感性について考え直した新しい認識や感性の学問が必要となってくるのではないだろうか。ニュートン以来の自由落下の方程式は地上でのみ有効な方程式であることが宇宙の存在によって明らかになった。そのことと同じような状況がまた新たに起きていると言えるだろう。カオス*ラウンジの活動は地上で自由落下の法則を無視し、自由に動き回ろうとする試みであり、それは地上では無理な話であった。宇宙空間でも通用する普遍的な方程式を発見する試みと同じく、私たちもまた新しい空間をも含む普遍的な認識論や感性論をもとに法や制度を見直す時が来ているのではないだろうか。
残念ながら今回は新しい空間であるインターネットとそれを支えるコンピューターの原理を分析し、新しい認識に対して仮説を立てることまでしかできなかった。今後は新たな感性と認識の学問の構築のため、より様々な事象から分析を行わなければならない。
すでにコンピューターとインターネットは私たちを覆いはじめ、爆発的な速度で発達し続けている。この変化をいかに食い止めて行くのではなく、どうよりよく発展させていくかが今後の人類繁栄のためになるのではないだろうか。
参考文献一覧
Lev Manovich「The language of new media」2002 The MIT Press
Rachel Green 「Internet art」2004 Thames & Hudson
Erin McglothlinLutz Koepnick「After the Digital Divide?: German Aesthetic Theory in the Age of New Media 」2009 Camden House
石坂 悦男、 田中 優子「メディア・コミュニケーション―その構造と機能」2005法政大学出版局
東 浩紀 「サイバースペースはなぜそう呼ばれるか+」 2011 河出書房
川野 洋 「ネットワーク美学の誕生‐『下からの綜合』の世界に向けて‐」 2009 東信堂
北野 圭介 「映像論序説‐<デジタル/アナログ>を超えて」2009人文書院
椹木 野衣 「増補 シミュレーショニズム」 2001 筑摩書房
吉岡 洋 「デジタルメディアの形而上学」 京都哲学会
吉積 健「メディア時代の芸術」1992 勁草書房