見る衝動/見させるパルス
発表日:平成13年10月17日 |
〈要約〉
モダニズムは視覚に見える所のみが重要とされ、追求され、見えない不可視な所は排除されていった。しかし、そういった見える所という可視な所よりも、見えない不可視な所にこそ追求されるべきものがあるのではないか?ということがこの論文にかかれている。そのことを謎解いていくために、リズム、ビート、パルス(オン/オフという一種の律動)の問題が提起されている。それらは視覚的空間の安定性を破壊し、その特権を奪うことを本性としている。なぜなら、視覚性を支えていると思われる形態(=形式)の統一性そのものを解体し、溶解させてしまう力がビートには備わっているからである。
第二)
モダニズムの視覚の論理を支えるのは「分離性」の概念で、モダニズムは感覚の分離を唱えてきた。それ故、モダニズムの観点においてビートは、時間的なもの、聴覚的なもの、言説的なものの領域からの不法な干渉で、いつも視覚的領域から排除されてきた。
|
|
「マトリクスは無意識に属しており、抑圧の背後で不可視的に作動する一次過程の形式である。そのため、防衛を経て形成された現想だけが、可視的なものの領域に浮上しうる。したがってマトリクスは、幻想がもたらす形象化にもとづいてしか、推測したり、再構成することが出来ない。」 |
それに対してモダニズムは、ほかのあらゆる感覚を排除して視覚的なもののみを分離し、自己充足と自律性を追求した。このマトリクスとモダニズムの関係はフロイトの無意識と意識の関係に例えることができる。フロイトはこころを意識・前意識・無意識という3つに区分し、無意識は前意識を通って意識に浮上してこようとするが、その際に必ず検閲をうけ、抑圧されたものが無意識に溜めらるため、意識の側から無意識を知ることは出来ないという。見ることが出来る意識の部分だけで完結させようとするモダニズムに対し、表層だけにとどまらず、意識を通してそれを構成した見えない無意識の領域まで見ようとする見方(視覚の可能性)をここでは提起しているのではないだろうか。
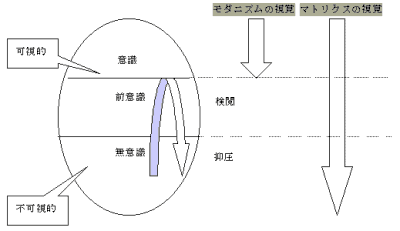 |
〈疑問〉
-
ロザリンド・クラウスはピカソやデュシャン、ジャコメッティの作品やフロイトの「子供が叩かれる」を例に出したとき、いつもそれらはエロティックな方向に結びつけられているのはなぜか?人間の幻想や無意識のうちでの欲望は常にエロティックなものなのか?
-
ビート、パルス、リズムの違いは何か?ロザリンド・クラウスはどのようにこの三つの言葉を使い分けているのだろうか?
-
p.88・6〜にあるように、ビートないしパルスが視覚の奥底で動いていて、視覚と区別されないのだとすれば、モダニズムが本当に視覚のみを分離させることは不可能なのではないか?
〈用語解説〉
-
リズム:
音の強弱などの、周期的な繰り返しによって表される秩序。律動。調子。節奏。 -
パルス:
きわめて短い間に流れる電流や電波。また、その繰り返し。Pulse=脈拍。
-
律動:周期的に繰り返される運動。リズム(にのって動くこと)。
-
ゲシュタルト Gestalt(ドイツ):
ゲシュタルト心理学の基本概念。全体を、部分の寄せ集めとしてでなく、ひとまとまりとしてとらえた、対象の姿。形態。 -
マトリクス matrix:
(発生・成長・生成の)母体、基盤。(ラテン語mater+-ix=子宮→母胎)
近代化する視覚
|
〈要約〉
視覚はこれまで歴史的に区分され、伝統の連続性を強調するやりかたで論じられてきたが、このような支配的な歴史観によって見落とされてきた非連続性の重要さをここでは強調したい。カメラ・オブスクーラいかに当時の支配的なパラダイムと重なり合って、見るもの(観察者*)の立場や可能性をイデオロギー的に規定していたかを、認識しなければならないからである。カメラ・オブスクーラは認識論においても、科学的な位置付けにおいても、何が知覚における「真理」なのかを映し出す装置と考えられていた。人間の視覚にはらまれた不確実さを排除することで世界に対する絶対確実な視点を与え、その視点から世界を体系的に説き表そうとするデカルトの探究に、カメラ・オブスクーラはぴったり合っている。そこでは都合の悪い両眼視差は軽視された。カメラ・オブスクーラの観察者*は、名目上は自由で自律的な個人だが、実はあらかじめ与えられた真理といわれるものに従属していて、外部から切り離された私的な単独主体でしかないのだ。
19世紀前半、これまでのパラダイムは崩れ去り、人間的視覚という全く異なったモデルに取って代わられた。視覚をめぐる言説と実践の中に、「人間の身体」が含まれるようになったのだ。ゲーテの『色彩論』では、視覚における中心は身体になり、生理学的身体に基づく主観的視覚というモデルが記され、生産力を持った新しい観察者が見出された。観察者の身体は視覚的経験を生み出す様々な力を持っているので、神経経験は観察主体の外にあるいかなる対象にも対応していない。視覚は生理学的プロセスと外的刺激とが絡み合って混合しているのである。
かつて、実在しない錯覚であると片づけられていた網膜残像などの経験は、19世紀前半には視覚を成立させる実定性になった。そして、視覚を生産する身体を特権化することによって、カメラ・オブスクーラが前提としていた内部と外部との区別が崩壊し始め、知覚と対象とが直接的に対応するという考えは揺らぎ、自律的な視覚のモデルが成立したのである。
19世紀に生まれた生理学の中で、眼や視覚のプロセスについての新しい知識に基づく新しい認識論的な考察が展開された。生理学は、知が身体(特に両眼)の肉体的・解剖学的な構造と機能によって条件付けられているのを発見し、組織や機能に応じて身体を次々に分割・断片化していった。感覚の分離が科学的に理論化され、古典的な観察者との間に決定的な切断が生じ、見る行為とは必然的な関係のない視覚を持った観察者という概念が生まれたのだ。
ヨハネス・ミュラーの「特殊神経エネルギー論」は、同じ原因(例:電気)であっても、それがたどる神経によって全く異なる感覚を生み出すと考えられる一方で、ある決められた感覚神経においては多様な原因が同一の感覚を生じさせることを示した。感覚は規則正しい立法的な機能ではなく、意図的な管理や攪乱を受け入れてしまう。この理論では内的感覚と外的感覚の区別が抹消され、古典観察者やカメラ・オブスクーラが以前持っていた「内部」の意味が失われた。 〈考察〉視覚の変容にともなう観察者の立場の変化
|